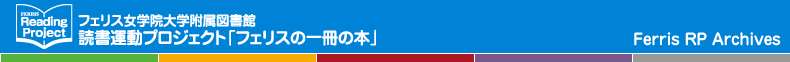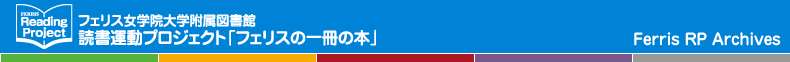|
 |
| ■
27-3・他者の競演/饗宴〜ダイアナ・ウィン・ジョーンズと同時代のファンタジーから-4 |
 |
 |
2005年6月27日発行読書運動通信27号掲載記事5件中3件目-4
特集:西村醇子先生講演会
 |
 |
|
 |
アブダラの話はこのくらいにして、三つ目の作品に入ります。
『呪われた首環の物語』(Power of three)という、1976年の作品です。
最初に紹介した『The Ogre Downstairs』の二年後ですから、
最近の作品に比べて単純ですが、部族間の文化の違いと、
視点の移動を含んだ面白い物語です。
これは、オックスフォードの東にあるオトモーア湿原が舞台になっています。
主人公は子どもたちです。聞きなれない名前をたくさん言いますので、
ご承知おきください。まず「太陽の民」といわれている人たちがいます。
その一家族の、長女エイナ、長男ゲイア、次男セリという3人の子どもが主人公です。
彼らは湿原の塚に住んでいますが、言葉を使って、たとえば塚を封印するような、
そういう特別な能力をもっています。エイナという長女は、“gift of sight”
という先見をする能力が、セリには “finding sight”という、
物を見つけたり人にエネルギーをぶつけたりできる超能力があります。
ところが二人にはさまれたゲイアという男の子は、本当は能力があるのに、
それがわかっておらず、ちょっとひがんでいます。
彼らの住んでいる所には、ジャイアントと彼らが呼ぶ「大地の民」がいて、
いつも大声を出し、また争っているため、ゲイアたちは恐れていました。
また太陽の民と、水の中に住んでいる「月の民」ドリグとは敵対関係にありました。
ある日、ドリグが攻めてきて、塚を占拠してしまったので、
太陽の民は居場所を失ってしまいます。ところがその争いの背景にはもうひとつ、
水争いの要素もありました。飲料水不足に悩むロンドンに住むジャイアントたちが、
その問題解決のために湿原地帯を貯水池にしようと計画している。
そうなると自分の農場が水没するので、それを防ぎたいと考えているのが
ジャイアントの子どもたちです。
私たちは最初、太陽の民の視点で話を読みますが、
彼らは自分たちを“people”と呼んでいます。彼ら太陽の民から見た
ジャイアントは――体が大きいから巨人ですが――、
要するに私たち「人間」のことです。作中ではジャイアントたちも
自分たちのことを“people”と呼んでいます。
自分たちがジャイアントのはずはない、ジャイアントなんて存在しない、
と主張し、逆に太陽の民は不思議な力をもっているのだから
フェアリーにちがいない、と言うのです。彼らから見れば太陽の民は
“little people”です。では残るドリグはと言えば、
彼らも自分たちのことを“people”と呼んでいます。
彼らはまた大地の民のことを「ダイマン」と呼びますが、
相手はそれに反発します。
大小が相対的なものであることが、これでよくわかりますよね。
そして、他者というものが、揺れ動いていく彼らの関係のなかで、
常に入れ替わっていくということも。そのあたりが
物語の面白さになっていると思います。
この作品には古代ケルト風の雰囲気が漂っていますし、
場所と密接に関わっているファンタジー作品です。
ジョーンズはファンタジー作品の舞台をあまり特定させないほうですが、
これだけは「オックスフォードの東」とはっきり設定されていて、
場所と密接に関係した展開になっています。たまたま太陽の民が
中心になっていますが、そうすると私たちが巨人にあたる
ということを教えてくれます。そして他者と接することで異化作用が起き、
自分たちを見つめなおすことができるわけです。
また、私たちが伝承の世界だと見ている人たちにも言い分がある
ということもわかる。さて、歴史的な経緯をもつ複雑な抗争のなかで、
お互いに憎しみが育っていました。それを取り除くのは何かと言えば、
言葉しかありません。登場人物たちは言葉によって話し合いをもち、
ネーミングへのこだわりを捨て、新しい理解を得ようとしています。
言葉がもつ力を前面に出すのは、ジョーンズの作品に共通するテーマのひとつで、
ソフィーが言葉によって魔法の力を引き出していた個所にも見られましたが、
ここでもそれが前面に押し出されていると思います。
歴史的な経緯は、ときに憎しみを育てる側面をもっています。
物語は、太陽の民の子どもたちの母親が子どもだった頃にさかのぼります。
うぬぼれの強い兄さんが、自分は偉いと見せびらかすために、
たまたま行き会ったドリグの王様の息子を殺します。
彼の首輪(トルク)をほしいばかりに。
そして「良いドリグは死んだドリグだけだ」と言って、
相手が人間であることを認めようとしなかった、それが発端だったのです。
その結果として、ドリグのかけた呪いが土地にしみこんだため、
徐々に皆が不幸になっていきます。物語の現在であるエイナやゲイアたちの
代になったとき、今述べた昔のいきさつに加え、住居と水の問題などの
要素が加わって、非常に紛糾する。そして、古き力・今の力・新しき力という
三つの力“power of three”の呪いを解かないと平和がこない、
というストーリーになっています。
ケルトの伝承が色々な形で使われていますが、それだけでなく、
長年の誤解とか恨みのもつ弊害、そして好奇心を持つことの意味や、
異文化交流のあり方といった、今日的な問題が、三種族の話の中に
活かされています。別世界でなく同じ場所を共有するひとたちが
三重構造になっている――この物語の作り方が、私には重要だと思われます。
結局、人間だけが地球の主なのではない、所有権があるわけではないという、
今日の環境問題へも通じるテーマを、作者は一九七〇年代に描いているわけです。
私たちはどこかで、生き物すべてに権利があることを見失ってきました。
環境問題を含めて、自分のいる場所や自分の文化を基準とし、
そうでないものを眺めてきたからです。それがこういうふうに
三つ並べられることによって、見方に転覆が起き、
価値観というものが相対的であるということを、嫌でも気付かされるわけです。
それぞれの部族の話が描かれるたびに、大小の感覚も含めて、
色々な見方が展開されていくというのが面白さになっています。
“power of three”という作品の原タイトルは、古き力・今の力・新しき力の
三つの力を鎮めるまでは、呪いが解けないという内容をあらわしています。
同時に、もう一つの意味が重ねられているでしょう。
おそらくは、それぞれの種族の代表という意味があると思われますが、
太陽の民のゲイアという、皆から理解されてないと思って悩んでいた男の子、
月の民の王子であるハフニンという男の子、さらに大地の民である農場主の息子、
ジャイアント(わたしたち人間代表)のジェラルド――この三人が、
それぞれ勇気をふるい、自分の殻を破って何かをしていった時に、
大人たちの考えを変えることに成功しているので――三者の力をも象徴していると
思います。三人にはまた、それぞれの父親と上手くいっていないという
共通点があります。これは大人と子どもの関係のなかで、
ときに起こることです。子どもは大人から見ればわけのわからないところがあり、
「他者」と言えますが、逆に大人から見れば子どもにも理解しきれない面をもつ
「他者」です。そういう関係にあって互いにちょっとづつ歩みより、
突破口を開いていくという物語でもあるのです。
話し合いによって解決に至るものだ、というメッセージを作者が物語に
こめていたことも、うっすらと見えてきます。
私は、最近読み返した時に、一つの可能性に気付きました。
先程、同じ場所に住まう人間とフェアリーたちという言い方をしましたが、
これを人間と動物たち、と見ることもできますよね。
作中で子どもたちがお互いにちょっとしか差がないのだから、
もともとは一緒だった種族が分かれたのかもしれないね、
と話し合う場面があります。そこを読んだときに頭に浮かんだのは、
ヨーロッパのなかのさまざまな人種の違いのことでした。
差異を超えて理解しあっていけるのでは、という思いが、
大きな戦争を経てきた作者の意識のなかにあったのではないか、
そんな気がしております。
|
|