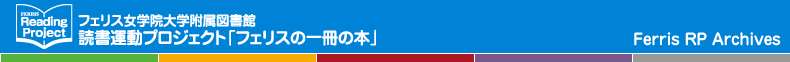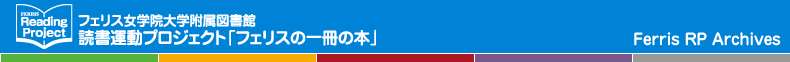|
| はじめに
|
 |
本が危機だとよく言われます。
本をめぐるゆるやかな時間が姿を消して、あわただしい時間のみが強調され、効率のみが優先されると、
本の享受はますます難しいものとなっていきます。
わたしの専門としています源氏物語でも、最近は全巻読んでいるという人がきわめて少なくなっています。
卒論を書いている学生さえ、果たして本当に全巻読んでいるのか疑わしい卒論もありますし、
放送局・新聞・雑誌・出版界では読んでいる人は皆無に近いでしょう。
時代が大作に厳しい時代となったのです。
その流れに抗うようにドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は新訳が出て、
若い女性を中心に久しぶりの大型ヒットとなりました。
時代は大作を嫌いつつ、どこかで「大作」を深く希求しているということになるのでしょうか。
そういう不思議なバランス感覚が働いていると感じる場面もあります。
しかし、大きく見れば、やはり、本をとりまく環境は年々厳しさを増しています。
出版の側から言えば出版点数の増加と売れないことで労働過重を長く強いられていますし、
流通の側から言えば大量の本を回転させるため,息もつけない重労働を強いられています。
斜陽どころか本屋の現場はほとんど「崩壊」しているというのが本の雑誌の
営業マン杉江由次氏の最近(2007.10.10)の悲鳴でした。
店員の疲労、人員削減、小規模書店が駆逐され、次々に大規模書店に変わっていく現状、
小さくても誇りを持って品揃えしてきた書店が次々廃業に追い込まれる中、
それでも書店員のやりがいと生き甲斐を求めようと「本屋大賞」などさまざまな企画をたちあげてきた熱血営業マンの、
悲鳴にも似た警告でした。
本の現場を支えてきた書店員さんたちが志を持ちこたえられなくなってきたのです。
教育の場ではコンピュータ教育はなされているのに、本を使いこなすやりかたを
じっくり教える時間と余裕がないことが言えますし、教員も相次ぐ大学改革で忙しく、
学生への教育力を衰えさせていると言えます。
弁解はできませんが、読書の指導などやるべきだとはわかっていながら、ついつい後回しにしてしまうのです。
図書館の側で言えば、館員の減少、非正規雇用の増大によって、司書たちが余裕を失って、
お客さんの(ウチで言えば学生)顔を見ているゆとりをなくしています。
仕事に追われて、せっぱつまった顔をしているので、学生さんも相談しにくい雰囲気を
自然と醸し出しているのです。恥ずかしいことですがこれが現状です。
また、本をきちんと買い、蔵書を構築していくという体制が崩れてきて、
図書館同士で貸し出し合えばいいのではないかという安易な解決が導入され、
本を見て、選んで読むという本に対するアクセスの機会がへってきたことも見逃せない変化です。
何を調べるのかわかっていれば、それもいい方法かもしれませんが、読書のきっかけとは、
書棚を眺め、うろつき、手触りを確かめ、周辺の図書などにも目配りして初めてもたらされるものが
大きいのではないでしょうか。
今、本を探すだけならば、アマゾンなどのブック・サービスにアクセスするのが一番早いのですが、
そこでは、たまたま出会い、拾い物をしたような知識と出会うことはありません。
図書の電子図書への転換も起こり、図書館自体が電子図書館というかたちでデータを配信する図書館も現れてきていますが、
それが利用者のニーズに対応したものであるという検証はまだなされていないようです。
そうした動きも含めて、図書館はかつてのような「本」を所有し、保管する場所ではなくなってしまっています。
津野さんが批判されたように公立図書館がベストセラーを何冊も何十冊も購入してしまうという問題もあるでしょう。
利用者第一主義にあまり徹していくと、図書館は読まれなくなった過去のベストセラー本の墓場にもなりかねません。
その結果、図書館自体の蔵書への愛着も誇りも衰退し、図書館サービスもかたちだけの流れ作業となっている観があります。
図書館が現代という時代に合ったスタンスを取り、しかもやりがいと生き甲斐のある場所となっていくためには
どのような発想の転換が必要なのでしょうか。
そのおおもとのところは複数の多彩なメディアが成立することで、本を読む人それ自体が少なくなっていったことに
原因があるのでしょう。
本の虫で、子供のころから現在まで、1日1冊以上本を買い続け、読み続けてきた私でも、
インターネットで調べたり、読んだりする時間が次第に本を読む時間と拮抗してきています。
インターネットで調べる方が時間の効率がよく、その利便性をいまさら手放すわけにはいきません。
こうした状況の中で、本を読むことはたくさんの選択肢の一つとして相対化されなければなりませんし、
本をめぐる状況はその役割に合ったサイズダウンをはからなければならないのかもしれません。
出版界も本が売れないからたくさん作り、ますます売れなくなっていくという負のスパイラルを
限りなく再生産してきた現状を考え直してみなければならないかもしれません。
図書館はそうして発行された無数の本をすべて買い入れるわけにはいきません。
とても選別できないほどの量なのです。
大学図書館もこれからはどう本を選ぶかということを、真剣に考えなければなりませんし、
そのすべてをストックできるかどうかということも考え直してみなければならないかもしれません。
大学図書館としてストックするべき本と、フローとして、時代の表層を掬い上げる働きの二面性を
使い分ける発想も必要かもしれません。
本が相対化される存在になったから、本を見過ごしておいていいわけではありません。
本というシステムは、知識、考え方を保存するものとして、大きな役割を果たしてきました。
電子情報が一瞬の機械の誤操作によって失われてしまうはかなさを持ったものだということは、
どなたも体験されていることでしょう。
記憶媒体の経年変化がどのくらいなものなのか、まだ検証されていませんから、
CDやDVDに焼き付けた情報も何十年後には保存できなくなっているかもしれません。
その意味では「本」は永続性のある文化です。
ものごとを筋道だって考え、論理化していく、他者の感情に気づき、それを繋げて考えていく能力を養っていく、
自分の人生の意味を考え、それを自分にも納得のいくかたちで自分に物語っていくためにも、
「本」や「物語」の存在は欠かせません。
12月5日にPISAの学力調査の結果が出て、2003年度についで、2006年度においても
日本の子供の読解力が落ちていることが指摘されました。
長い文で複雑な内容を繋げて考えることが日本の子どもたちには苦手となっていることがわかってきます。
新聞などの論調によりますと、そのような状況を生み出したのは日本の国語教育が文学偏重となっていることに
原因があるとされました。
それでは国語の場から文学を追放し、実用的な伝達文ばかりを読ませれば、
子どもたちの読解力は回復するでしょうか。到底そうは思われません。
なにかを繋がりのある意味の場に置き、関係づける働きそのものに「文学」も深く関わっているからです。
さまざまな知識をバラバラのものとして、脈絡なく覚えるよりも、自分にとって意味あるものとしてつなげていくことで、
知識は生きた知識となっていきます。
小説や物語のフィクションはそうした意味連鎖のゲームを遊ぶこと、
納得できる筋道を考えるロールプレイゲームの訓練の場でもあります。
PISAの調査で最高位を占め続けたフィンランドの教育が「本」を読むことを基本とし、
落ちこぼれを出さないことを目標に、地道な読書体験の積み重ねを基盤にしたものであったことは、
現在では広く知られています。
関連づけの中に置かれた知識は、生きた知識として、経験と折り合わせられ、活気付けられて、
脳内のニューロンとニューロンを結びつける力を強くしてくれるのでしょう。
「本」を読む力の衰退は、「本」を読むことがITの技術に劣らない高度にして複雑な技術でもあったことを
改めて教えてくれます。
一度にたくさんの知識を得るのではなく、1本の線上をたどるように、ゆっくりと時間をかけて辿られる読書の時間は、
そうであるがゆえの豊かさを持っています。
情報が少なく、持続的であることで、思考が整理され、活性化し、発想が豊かに展開していくという逆説です。
「本」を読むということはこの情報の絞り方に付き合い、歩みを共にして、対話をするように
みずからの考えを手繰り出していく過程に他なりません。
その時間も余裕も現在ではなくなりつつあるのです。
子どもたちの読書が足りないということに警鐘が鳴らされていると申しましたが、
実は子どもたちよりももっと本を読まない人がいます。中年の働き盛りの人々です。
それも男性よりも女性の方がもっと読んでいないということが読売新聞の読書調査では明らかになりました。
子どもを育てる両親が「本」を読まないということであれば、「本」の文化の継承はおぼつきません。
大学における読書運動は、そうした次世代に繋がる「読み」を耕し、種を蒔き、育てる最後のチャンスでもあるのです。
|
|