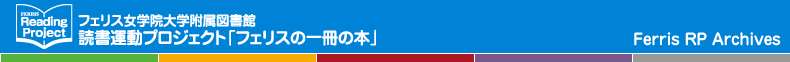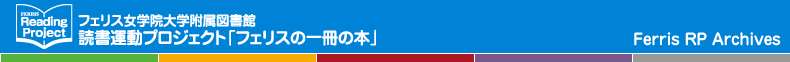|
| 松田2
|
 |
出版界は多産多死と言われています。
読書離れが進行中の今、そんなにたくさん本を出してどうするのかと、
本を作っている側もそんなことを言っていますけれど、
それでも大事なものを守っているんだということは心に留めておかなければ
いけないなという気はします。
が、出版社が在庫を持ち、売り続けるということは、管理コストがかかりますし、
ある程度売れている本になれば税金もかかりますから、ある年数以上在庫としてあれば、
利益がなくなっていく、逆にマイナスになってしまう場合もあって、
あまり長く在庫を持ち続けられないというのが現状なのです。
ですので、図書館で、ベストセラーだけではなくて、残すべき本をピックアップしていただいて、
次の世代に伝えていっていただくなど、出版界ができる出版文化の守り方と、
図書館ができることとがうまく組み合わさっていけばいいなと思います。
出版界のことでいうと、ここ11年間、売り上げが右肩下がり、毎年マイナス成長、
まあ、大きい年だと5%くらい落ちた年もありますが、ここのところはだいたい2%か3%、
今年もだいたい3%くらいのマイナスだろうと見こまれています。
業界的に言いますと、いわゆるコミックの新書版というのが雑誌扱いになっていて、
それも含めて雑高書低、雑誌のほうが圧倒的に売り上げが大きく、
書籍はシェアが小さいというのが、ここ20年くらいの傾向です。
そして、この11年間で顕著なのは、雑誌が非常に急速な落ち方をしていることです。
(書籍の方は、この11年間で1度か2度、『ハリーポッター』が出た年ですが、若干プラスに転じた年があります。)
これは、皆さんもおわかりのように、いわば雑誌に代わるものがどんどん出てきているからですね。
インターネットが1番わかりやすい例ですが、フリーペーパー、フリーマガジン、
お金を出して雑誌を買わなくても、無料配布の雑誌に、結構質の良い情報が掲載されているし、
娯楽性もあるということで、総合誌的なもの、男性週刊誌的なものがどんどん落ちていっています。
かつては、メディアとして古くなりダメになった雑誌は、廃刊にして新しい雑誌を創刊したりしていたのですが、
今ではそういうこともできなくなってきています。
ではそういうことを背景に、出版界で何が起きているのかというと、新書ブームなんですね。
新書には教養系新書、ノベルスと呼ばれる小説の新書や、かつては生活実用系新書というか、
カッパブックスのような、いわゆる教養ではない新書もあったのですが、
現在では、教養系新書というものを各社が刺激しあってブームを形成しています。
|
|