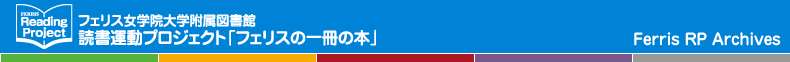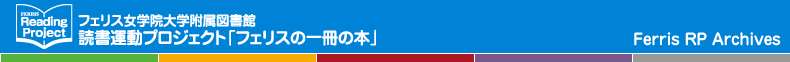|
| 松田3
|
 |
岩波書店が岩波新書という形で始めた教養系新書は、
中央公論新社の中公新書と講談社の講談社現新書の三つくらいしかなかったのですが、
ここ10数年間の間に、私のいる筑摩書房を含め、新潮社、文藝春秋、集英社などの大手をはじめ、
さまざまな出版社が参入してきています。
でその理由は、ある意味わかりやすいことなんですが、
一つは出版社の人員配置の問題です。
要するに、総合誌や男性週刊誌的なものを作る編集者が余ってきているので、
一番雑誌に近い書籍である新書に彼らが配置されるからです。
普通の単行本というのは、各社で違いはありますが、
普通、原稿用紙300枚〜400枚以上の分量です。
作家から原稿をもらってきたら、それにビジュアルを加えたり、
資料を加えたり、装丁を考えたり、デザイナーに発注したりと、
やることはたくさんあって、その一つ一つをしっかりやっていかなければならない。
雑誌の場合だったら、雑誌はあらかじめフォーマットが決まっていますから、
編集者が原稿をもらってきたら、そこにどんどん放り込んでいけば作れるという、
ある意味簡単なのです。
単行本は、なかなかそうはいきません。
経験も必要ですし、センスも必要、ましてや、複数の著者や編集者と
チームを組んで作ることにでもなれば、難しい作家と付き合いながら原稿をもらってきたり、
編集であれこれ作業したりと、バラエティ豊かな仕事なのです。
そこで、新書に戻りますが、教養系新書というのは装丁が大概一定しています。
いわばユニフォームがあって、タイトルと著者名とキャッチコピーを書いていけば、
装丁デザインなどで思い煩う必要がない。
出版社によっては、新書は原稿さえ持ってくれば、あとは流れ作業でやれてしまう。
それぐらい編集者に負荷のかからない仕事なわけですね。
それから、新書隆盛のもう一つの理由は、雑誌のかわりに、雑誌の特集とか連載とかを
一つずつバラして、新書という形で出していると考えることもできると思うのです。
この時代に必要とされるもの、必要とされていることは何かをさぐり、
そのテーマにふさわしい書き手を見つけてくるのは、雑誌の仕事と非常に近いことですから。
そうして教養系新書がどんどん膨らんでいくと、面白いことがおきはじめます。
教養系とはいえないコンテンツまで入ってくる。光文社が象徴的なんですけれども。
光文社では、大変なベストセラーを生み出したカッパブックスという新書のシリーズをやめて、
光文社新書というものを作った。
『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』とか、『若者はなぜ3年で辞めるのか?』とかが
そうなんですが、そこにはカッパブックスのセンスが現れています。
今、新書を出している会社は十数社あると思いますが、
その中には教養系新書といいながら、かなり飛び離れた内容になっているものもあります。
そのようにたくさんの本が出てその市場が活性化されると、
賑やかな市場があるジャンルからは売れる本も出てきますし、
意外な発見があることもあるんです。
さて、今の出版界の状況を見ていると、新書に比重が偏りすぎているので、
新書の次にくるものはなんだろうかと、考えたくなるわけです。
|
|