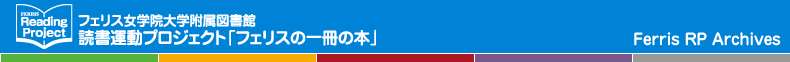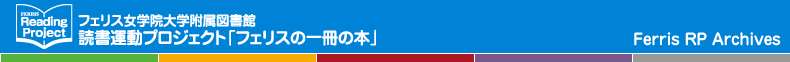|
| 津野3
|
 |
市民図書館運動はすばらしい運動でした。
そして、その活動の根幹には、保存至上主義から利用中心主義に変えていこうという理想がありました。
ただ問題は、そのすばらしい理想の背後で、「保存」という図書館のもう一つの基本理念が、
なんとなく日陰の存在になってしまったことです。
リクエストが多いのでベストセラー本をたくさん買う。いいでしょう。
でも、そういった本は、流行がすぎればすぐに読まれなくなってしまいます。
当然、廃棄することになります。
そういったことが度重なるうちに、だんだん、図書館側にも廃棄に対して馴れが生まれて来てしまうのですね。
さっき松田さんが話してらっしゃいましたが、出版社はどんどん本を出します。
売れ行きが下がると、出版点数で稼ごうとするからです。
その結果、図書館が購入しなければならない本、廃棄しなければならない本が増えてしまいます。
市民図書館運動の理念は正しかった。
しかし、どんなに正しい理念でも、時間が経てば、それをとりまく状況が変わってくるわけですから、
ある程度の修正を加えていかなければなりません。
かわらないでいるためには、いつもかわっていかなければならない。
正しい原則をいつも健康的に維持しようとすれば、少しずつかえてかなければならないということです。
そうすることで、はじめて、最初の理念を長く生かすことができるのです。
そのことを象徴的に示したのが、2002年2月、東京都庁が発表した、都立図書館の再建計画です。
世の中の変化に対応して、図書館を新しくしようという意図らしいのですが、
かつての市民図書館運動とは中身が全然違いました。
東京都には、都立中央図書館、都立多摩図書館、都立日比谷図書館の3館があり、
その3館が協力して都全域の地域サービスに当たるというシステムになっていました。
そうなると、東京都は広くて人口も多いですから、3館が同じ本を複数所蔵しているということも
往々にしてあるわけですね。
ところが、2002年、石原慎太郎都知事から、3館が重複して持ってる本を段階的に廃棄せよ、というお達しが出た。
本をこれ以上増やさない、そのための予算は大幅に削減する。
今後、新規購入は3館合わせて1冊だけにしろと言うのです。
手始めに、重複の14万冊を廃棄せよという命令が出て、ただちに所蔵目録から抹消されてしまいました。
いくら検索してもデータはもうないので、貸し出しも出来ないわけです。
ただし、現物はまだ残っています。
町田市立中央図書館の手島さんという男気のある館長さんが、
半数の7万冊をしばらくあずかってくださることになり、
残りの分も多摩地区の図書館員有志の努力で、なんとか捨てないようがんばっています。
その上、都立中央図書館の市町村立図書館への協力貸し出しについても、
金がかかるから送料は利用者負担にするとか、職員の新規採用を大幅に減らして、
コンピュータや業務委託に置き換えていくとか、さまざまな計画が実行に移されています。
その結果、現在、資料費は60%くらいまで削られ、職員の新規採用も2002年以降やっていません。
団塊の世代以降の図書館員が6割を占めるのに、彼らが退職したあとの
補充の予定がないのです。
当然、書庫の増設なんてするはずがありません。
いくら3館合わせて1冊ずつしか本を買わないようにしても、増えていく本の量は
凄まじいですから、受け入れる余地がなくなってしまいます。
いくら廃棄しても、それで空いたスペースなどたちまち埋まってしまう。
そこで1冊しか買わない本まで廃棄したら、その本は図書館から完全に消えてしまいます。
つまり、図書館の重要な機能である「保存」という任務を放棄してしまうことになるのです。
|
|