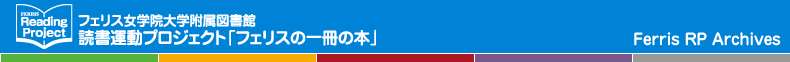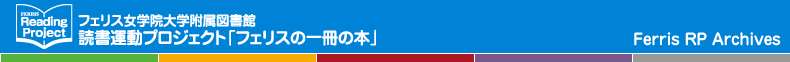|
| 津野4
|
 |
市民図書館運動のおかげで、保存中心主義から利用中心主義へ、図書館は大きく変化しましたが、
今は利用中心の考え方までが形骸化し、利用者にも不便がかかっています。
この先、図書館そのものが形骸化してしまわないためにも、
「保存」の重要性を再確認しなければならないと私は思います。
『源氏物語』をはじめとする文化資産をきちんと保存していく。
それは当然なのですが、新しく生まれたばかりの本も、同じように保存し続ける必要がある。
たとえば、現在、筑摩書房には90人くらいののスタッフがいて、
年間400点からの本を発行しています。
その400点の本はまず商品として世の中に出るわけですね。
大小の取次会社を通して書店に並べられ、読者はお金を払ってそれを購入する。
その売上げで、著者も筑摩書房のスタッフも、印刷会社も書店もようやく生計を立てている。
皆さんがお金を払って買うという行為は、それほどに重要なものなのです。
それなのに図書館に行けば同じ本がただで読める。
10円コピーも簡単にできます。
なぜ図書館では、ただで本が借りられるのか、それは、図書館が本を「保存」しておいてくれるからです。
国立国会図書館は、本をいつでも利用可能な状態で半永久的に保存するという義務があります。
200年前に出た本を読みたいという利用者がきたら、
それを適切に提供しなければならないわけです。
そのために出版社は、新しく出した本を必ず1部、国立国会図書館に納めなれればならない。
そう国立国会図書館法で定められているんですね。これを法定納本制度と言います。
つまり、本というものには商品としての価値だけでなく、文化資産としての価値があるのです。
日本では著者が死んで50年経ち、著作権が消滅したときに、
本の商品としての価値は消滅し、誰でも利用できるようになります。
他方、図書館は本が誕生した瞬間から、それを無料で扱うことができます。
ただ、その代わりに、受け入れた本をできる限り長く、最上の状態で保存する義務を負わされる。
それは国立国会図書館に限ったことではありません。
日本の図書館システムが協力してそうする義務があるんです。
本を作る側も、商品を作っているという意識のほかに、
文化的な財産となりうるものを作っているという意識をもっています。
自分の作った本ができるだけ広く長く読まれ、保存されたいという望みは、
だから、自然なことなんですね。
作家や編集者が死んでも、出版社が倒産しても、本だけは生き残り続けるわけです、
図書館という働きによって。
商品としての本は、流通販売のシステムに支えられていますが、
文化的資産としての本に対する「長く保存され、読み継がれたい」という夢を支えるのが
図書館です。
だから図書館は、本をただで貸すことができるんです。
「保存」は図書館の義務です。
できるだけ「保存」し続けて、できるだけ多くの人にそれを「利用」してもらうのが、図書館の仕事なのです。
利用者にも、そのことを意識してほしい。
安易な気持でリクエストをし、図書館の負担を増やすのはいけません。
自分で買ったり、友達とお金を出しあって買って、回し読みをすれば、
図書館も出版社も皆さんも助かるのですから、そういう意識をもってください。
でないと、出版社も図書館も潰れてしまう。
利用者だって責任はあるんです。
その自覚がないと、図書館は潰れてしまいます。
東京の図書館は、利用者もしょせんは消費者だと甘く見られています。
では、どうしたらいいかということは、この後のシンポジウムで語りましょう。
|
|