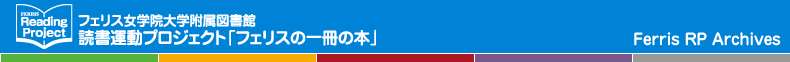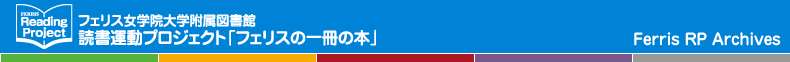|
| 津野5
|
 |
そうですねえ。私は、津野さんと『本とコンピュータ』の編集にかかわり、
パブリッシングリンクという電子出版の配信会社の社長もやっていました。
でも、出版、紙の本を作っている立場で言うと、たくさんの本を作っても、
ほんの一部しか残っていかないというのが現状ですので、
図書館には、本を捨てずに大事に保存しておいて欲しいというお願いがあります。
図書館の保存機能なくして出版文化というものは次の世代に届けていけないと思います。
今の本作りを考えると、印刷の前段階、プリプレスまでは、もう完全にデジタル化されています。
かつてアナログでやってたころとは相当の様変わりです。
ですから、本は消えてもデータを保持することは不可能ではない。
データをキチンと保存し、いつでも読めるようにすることが、
今後、もしかすると出版界の責務の一つになるかもしれません。
が、保存するだけでは、企業としては全く採算が合いませんから、
何らかのビジネスにつながるといいなというのが淡い夢としてあります。
ここ10年くらいの間に、電子出版ブームというのが何回かありましたが、ビジネスモデルを描けず、失速しています。
一方、ケータイ読書はですね、こちらはかろうじてビジネスに届きそうな感じがあります。
地味な本、現時点では評価されていない本も、データさえ保存しておけば、10年先20年先に、
非常に多くの読者を獲得し、大ベストセラーに生まれ変わる可能性もあります。
しかし、残念ながら、まだまだ電子出版なり、デジタルなりで読書をするのは
定着するとは思えないというのが現状です。
ところで、一昨日、今年の出版界を回顧するという話を、数人でしました。
出版社が本を作り、取次店ぎがそれを流通させ、それから書店に並ぶというのが、
今の出版流通のやりかたです。
そうなると、パターン配本で同じような本が同じような規模の店に並ぶ、
いわゆる金太郎飴書店と言われるような没個性な書店が増えるわけですね。
その構造はあまり変わっていませんが、その中で、意欲的な書店員が、
自分達がおもしろいと思った本を売ろうと、POPを立てることをしはじめました。
『世界の中心で、愛をさけぶ』とか、『白い犬とワルツを』とか、
これは千葉県習志野市の書店「BOOKS昭和堂」が仕掛けたものですね。
『天国の本屋』は岩手県の「さわや書店上盛岡店」がPOPで紹介し、
それがベストセラーのきっかけになったのです。
こういったことから書店員の手書きPOPで本を紹介する方法が、
全国的に広まっていきまして、1994年に新潮文庫から出た志水辰夫の『行きずりの街』が、
突然何十万部も売れたり、わが社も、1986年初版の外山滋比古の『思考の整理学』という本が、
やはり「さわや書店」さんからはじまって、数十万部売れています。
我々はどんどん新刊を出し、それの売り上げを延ばすことに重点を置いてきました。
その陰で、過去に出した本を、ちゃんと見直すという、とても重要なことがなかなかできずにいました。
書店や図書館の人たちが見直してくれることによって、こういう読者のニーズがある、
こういう本が求められているんだということがわかり、ならば我々編集者も、
そういうニーズに応えられる本を出そうじゃないかということになってきます。
出版流通的にいえば、上から下へ流れていくばっかりだったのが、いい意味で逆流というか、
コミュニケーションができるようになってきたことについては、希望を感じます。
図書館でも、POPを立てておススメの本を並べたり、
その時々のニュースにあわせて棚を作ったりとか、もっともっとやっていただければ、とてもいいと思います。
|
|