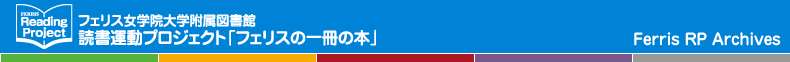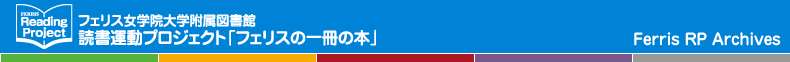|
| 三田村
|
 |
私も『カラマーゾフの兄弟』が売れる現代というのがおもしろく、興味深いと思っています。
あのような重苦しい超大作が、この軽い現代に改めて必要とされていると感じますね。
村上春樹がインターネットでカラマーゾフの兄弟を読む人を募って、四六時中、
『カラマーゾフの兄弟』の読書仲間に入れるという運動をしてますが、
そのハードルを越えた人と越えなかった人がでてくるのかなと。
司会が下手で申し訳ないですが、津野先生がおっしゃった、町田図書館の問題は、
図書館のとても重要な問題ですよね。
日野図書館を中心とした図書館運動に題材をとった『図書館戦争』という
本がありますが、お読みになりましたか。
津野
読みましたよ。面白かったです。
図書館の人たちが喜んでいたので読んでみました。
あれだけ図書館の人たちが喜んだのは、今までは図書館というものが、
あまりにも格好悪く書かれ過ぎていたからだろうと思いましたね。(笑)
三田村
そうですね。
その、日野図書館を中心にした自衛隊の戦争みたいな3部作が、今、評判になってます。
図書館が「保存」を大事にするか、「利用」を大事にするか、
難しい問題があるんだなと思わされます。
今の時代が、環境の大きな変化によって、自分達の世界、それ自体の存続が危ういと、
若い人たちの間にも不安があるのではないかと思います。
図書館を多元的に考え、本を残していかなければと思います。
それでは時間がきましたので、会場から意見をいただきましょう。いかがでしょうか。
来場者
国立国会図書館のSと申します。大変興味深くうかがわせていただきました。
津野先生には納本制度の紹介までしていただきまして、ありがとうございました。
先ほど松田さんのお話しの中で、興味深いなと思ったのは、
新書の流行の先に何が来るかということです。
新潮社は四六版の骨太の教養に還っていくという表現でいいのかなと思うのですが。
また、大学全入時代にあって、大学がリベラルアーツを復活させる動きがあります。
そういう中で、新潮社が取り組んでいる骨太の教養の復活というものが、
本当に残るのかどうかということをお聞きしたいです。
津野先生には、今のこのような流れの中で、公立図書館が深い教養というものに耐えられる
存在だろうか、また、耐えられる存在であるにはどうしたらいいか、そのへんを伺いたいです。
三田村先生には、大学がリベラルアーツで勝負することは、基礎体力を問われるようなもの、
その大学の力を問われることになると思うのですが、その中で大学図書館は
どのようなことができるとお考えになるか、お聞きしたいです。
|
|