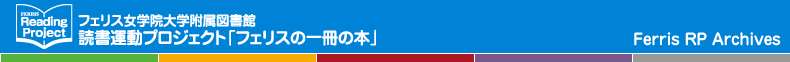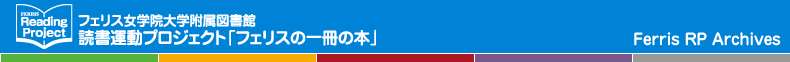|
2006年7月3日(月)11:30〜12:45
場所:附属図書館緑園本館4階読書運動プロジェクトミーティングルーム
ナビゲーター:安藤恭子先生
記事:国際交流学科3年 日隈亜衣子
 |
 |
|
 |
クラムボンとは一体何か。これが『やまなし』を読み進めていく上で
重要な要素だった。ある人は「泡」、ある人は「架空の動物」など、
様々な予想がされた。
多くの人が「クラムボンは泡ではないか」と主張する背景に、
『やまなし』を小学校で読んだことがあるという経験がある。
参加したメンバーの多くが小学校の国語の時間に読んだことがあり、
記憶のどこかでクラムボンを泡と記憶している。
しかし、クラムボンは読み手によってどの様にも解釈可能であり、
決して泡とは言えないのだ。私達の多くは小学校時代に先生から教えられ、
自分一人ではなく団体で読んだことにより、「クラムボンは泡」であるという
先入観をもってしまったのかもしれない。
今までは、まったく気付かなかったことだけれど、私達は先入観を持つことで、
自分自身の考えを打ち消し、「泡」という誰かが言い出した
予想を支持しているのだろう。
宮沢賢治は独特な世界観を出すことで、自分の考えを表現している。
しかし、その世界観が独特すぎることで、簡単に彼が何を伝えようとしていたのか
読み取ることはできない。毎回読書会を行うたびに、これほどまでに
自分自身の想像が人によって違う本があるだろうかと感じる。
人によって違いすぎるから、様々な憶測が飛びかい、実りある会話ができる。
今回はクラムボンとは何であるのかを話してきたが、それが何であるのかは
私達にもわからなかった。安藤先生もわからないとおっしゃっていた。
その中で、私達の考えは様々な方向にひろがり、
私達自身の解釈の仕方も変わっていった。
けれど、そのあいまいで分かりにくい世界観があるからこそ、
読み手の世界観を広げられるのではないだろうか。
|
|