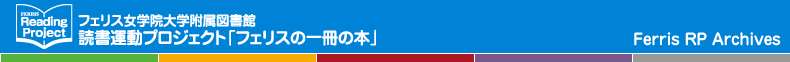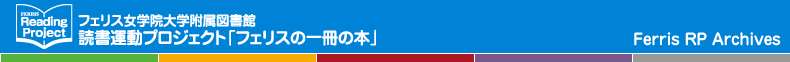|
 |
| ■
33-3・本を読んで考えたこと〜随想コンクール結果発表-1 |
 |
 |
2006年6月30日発行読書運動通信33号掲載記事9件中3件目
特集:コンクール結果発表(随想コンクール・ポスター標語コンクール)
紹介:宮沢賢治の本〜第1回
募集:創作コンクール、賢治の世界・イメージ展
 |
 |
|
 |
| 「『銀河鉄道の夜』しあわせさがし」を読んで〜「知らないこと」の強さ
|
 |
日本文学科3年 吉澤小夏
1.はじめに
『銀河鉄道の夜』に込められた、作者宮沢賢治の問いを読み解いていくのが、
この作品である。「神なき世界へ」「友だちって何?」「自己犠牲」、
3つに題された章から、賢治の問いに近づいていく。
この作品を読んで、ジョバンニが背負う賢治の思想を知った。
それはあまりにも深く、幾重にも考え抜かれていて、
到底すぐには理解できるものではなかった。しかし、この作品を読んで、
わからないことだらけだった『銀河鉄道の夜』というテクストの幻想世界、
賢治の思想に近づくことはできた。この作品が解いていく賢治の思想を考え、
それを込められたジョバンニの行動と比べると、ジョバンニ自身は
「何も知らない」ことから確かな意思にたどりついていることがわかる。
このテクストが私たち読者に与える「わからない」という感情は、
そんな、賢治の思想を背負わされながらもそれを知らずにいたジョバンニの
「わからない」につながるのではないだろうか。
2.「神なき世界へ」、知らないことの強さ
第1回の章では、テクストの初期形に登場したブルカニロ博士が
、
最終形への変更で消されていることを取りあげている。
そして、それが意味するのは「俗人へ」ということだと述べる。
ブルカニロ博士は、「ジョバンニが経験していることの意味を
わかりやすく説明する」役割を担い、またそれは読者への解説にもなっていた。
何でも知っている彼は、「超越者=神様みたいなもの」であり、
初期形でのジョバンニはそんな超越者に選ばれた存在になる、こう作品は指摘する。
ジョバンニは、賢治の思想をつぶやく、賢治の思想を担う人物である。
すべての生き物の幸せを求めるのである。
「すべての生き物のほんとうの幸いを追求する人物が、
初期形までのジョバンニでは、問題が発生します。初期形のままだと、
すべての生き物の幸いの追求は、超越者に選ばれたジョバンニにこそ
ふさわしいことになります。それが問題なのです。」
このように筆者は述べ、ジョバンニが「俗人」になるためにブルカニロ博士は消え、
博士から金貨を得るかわりに印刷所で働いて銀貨を得るジョバンニは
「プロレタリア」なのだとまとめる。「賢治が生きた時代に起こった
共産主義運動は、革命の主体は労働者であるはずなのに
それが一部の知識人に担われる矛盾の問題である、それと同じで、
すべての生き物の幸いは、全生物が考えることであって、
特定の誰かに担われるべきことではない、だからジョバンニは
特定の人間になってはいけなかった。」筆者はこうも述べ、ジョバンニは、
労働者の価値を訴えた賢治の思想も担っているとわかる。ジョバンニは、
俗人であり、プロレタリアである。そんな彼が、すべての生き物の幸いを願う。
言い換えれば、誰もがすべての生き物の幸いを願ってよいということだろう。
テクストの中でジョバンニは、賢治の思想を体現しながらも
ただ私たちの近くにある、という枠が見えてくるのだ。
もうひとつ考えたいのは、筆者がブルカニロ博士の消滅した意味に加える、
「世界を支える超越的なものなどない」という意味である。これは博士という
超越的なものが実際最終形で消えたことからも明らかであるし、
作品が指摘するように「かほるたちの提示した神も、カムパネルラが
指し示した『天上』もジョバンニによって否定」されることからもはっきりする。
ジョバンニは、どんな神も信じず、本当の幸せを探し求める。何かしらの神を
信じたりした状態でなく、何も信じていない状態にいる。それはつまり、
何も無いまっさらな状態であるということだ。いわば「知らない」状態に
ジョバンニはあるということだ。そんな彼がすべての生き物の幸いを願う。
私たちの身近な立場にいて、テクストをまっさらな状態で
読んでいく私たち読者と同じように「知らない」状態にある。
ジョバンニは私たちと近いことがまたわかるのである。
まっさらな状態であるということは、何かにすがっておらず、
自分を信じているということだ。白は染まりやすいが、まぶしく、
新しいものを作り出す色である。染まりやすい、ということはつまり
、
かほるたちのキリスト教、カムパネルラが親より先に死ぬ不孝を嘆くような仏教、
といった異なる宗教を受け入れることができる。一方で、新しい考えを
打ち立てることもできる。ジョバンニは、他人の考えの受容ができるが、
それを噛み砕いて新たなもの、すべての生き物の幸せを願うことを
実現させる可能性をもつ。「知らない」ことのもつ強さを、
ジョバンニは私たちに示しているように思う。
3.「友だちって何?」「自己犠牲」、知らないことは生き続けること
「知らない」状態からジョバンニは旅を続け、さまざまなことを学んでいく。
作品は、ジョバンニがかほるという第三者を介することで
カムパネルラの価値を見出す、ということにはジラールの理論があると述べる。
そしてそのあとにくるカムパネルラとの別れは、偶然に出会えば別れ、
それは続いていくこと、「人は偶然の出会いそして別れを繰り返すものであること、
そしてそうして出会った者に愛を注ぐものであることを意味」
していたと筆者は述べる。
ジョバンニは、カムパネルラとのかかわり、介入してきた第三者を
含めたかかわりも通して、多くのことを知っていく。そして知っていったことは、
人との出会いと別れは続いていくものであるということであり、
生き続けていけば出会いと別れを繰り返しさらに知っていく、
という逆のしくみも見えてくる。「『銀河鉄道の夜』をよむ」読書会で、
ある人が、「ジョバンニは人とのコミュニケーションを通じて欠落したものを
取り込んでいく」と話していた。欠落した、無いもの、知らないことがあるから
人は人と関わり続けるのだろう。「欠落したものを取り込む」という意見は
大変印象的だった。ジョバンニはやはり、賢治の思想を背負いながらも
わかりきれずにいることがあり、だからこそ旅を続け、同じようにわからずにいる
私たちに何かを伝えようとしている。わかりきれずにいるから人のなかで
生き続ける、このこと自体賢治の思想なのかもしれない。
最終章「自己犠牲」で筆者は、自己犠牲的な死をとげたカムパネルラたちよりも
ジョバンニが遠くまで鉄道に乗っていられたのは、「生者か死者の違いしかない」と
述べる。もう命をザネリのために捨ててしまったカムパネルラと違って
生きているジョバンニは、「『みんなの幸』になることが、ひょっとすると
できるかもしれない。そういう可能性をもっているという点だけで、
カムパネルラよりも遠くに行くことができた」、こう述べられている。
最後に賢治が重きをおいたのは、「生き続けること」だった。
生き続けていればこそ、何かを得ることができる。生き続けよう、
これこそが、ジョバンニが背負い、体現した賢治の根本的な思想だったのだろう。
4.おわりに
テクスト初期形に、こんな文章がある。
「みんながめいめいじぶんの神さまがほんとうの神さまだというだろう。
けれどもお互いほかの神さまを信ずる人たちのしたことでも涙がこぼれるだろう」
ここには、テクストの伝えようとすることがつまっているように思う。
神や超越的なものを超え、まっさらな気持ちになった時、だれがどの宗教かなんて
関係なく涙は出るじゃないか。人は人のなかでまっさらな、
知らない心同士ぶつかり、生き続けていけ、そう呼びかけているように感じる。
この「『銀河鉄道の夜』しあわせさがし」を読んで私が考えたことは、
宮沢賢治が、幻想世界で彩られた『銀河鉄道の夜』という作品から、
私たちに自らの願いをまっさらな気持ちで拾い上げてほしいと
伝えているのではないかということだ。本当にまっさらな気持ちで読んだ時、
生き続けるジョバンニがひょっとするとみんなの幸になれるかもしれないように
、
ぴかぴかの鉱石を拾い上げることができるのかもしれない。
|
|