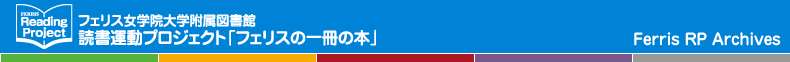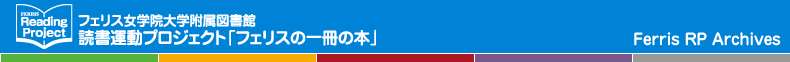|
 |
| ■
33-4・本を読んで考えたこと〜随想コンクール結果発表-2 |
 |
 |
2006年6月30日発行読書運動通信33号掲載記事9件中4件目
特集:コンクール結果発表(随想コンクール・ポスター標語コンクール)
紹介:宮沢賢治の本〜第1回
募集:創作コンクール、賢治の世界・イメージ展
 |
 |
|
 |
| 第二席『夜のピクニック』を読んで考えたこと
|
 |
国際交流学科4年 市川千鶴
人生は本当に、思い通りにならない事だらけだ。信じることの出来ない、
耐え難い現実を不条理と呼ぶのであれば、私たちはその不条理の塊の中で
生きている。空想の中に自分を見出し、もし自分がこうであったらと
仮の姿を想像しては、突然風船が割れるかのように、何かのきっかけによって、
今ある現実の世界に引き戻され、落胆する。
融と貴子もおそらく同じなのだろう。彼らは、生まれた時から既に厳しい現実に
突き放されていた。自分達が実は異母兄弟であるという、耐え難い現実を背負い、
誰にもその苦しみを見せることなく、自問自答し、ありのままの世界に
ただただ呆然とするばかりであった。自分がもし相手の立場だったらと
考え出す程になったのは、歩行祭が始まってからの事である。初めから上の道を
歩くように定められた者の憎しみと、下の道を歩くように指示された者の
哀しみとは、まったく異質な痛みであるかのようにすら思える。互いに
自分の身を引き合い、接点を持たないようにしてきたこれまでの二人の様子には、
彼らのどうする事も出来ない現状への苦悩と葛藤が痛ましいまでに表れている。
もう既に開ききってしまって、完璧に理解し合うはずのない二人の傷の痛み。
しかし、いざ心に少しのゆとりを持たせ、相手の立場に立って互いの気持ちを
考えてみると、その痛みは自分の持っている重苦しさとほぼ同じような痛みで
あることに気付く。それは、憎しみ合い、敵対視してきたライバルが、
突然自分の目の前にはっきりとした輪郭を保って現れてくるようで、それゆえ、
彼らはすべてを許してしまうのが急に怖くなり、何度も背を向けては、
ただひたすら痛みを麻痺させるまでに先を急ぎ、歩いて行こうとするのだ。
不条理の代表的な一つの例として、「融の父親の死」がここで挙げられている。
父親が亡くなったことは、融にとって理解に苦しむ、怒りと悲しみに満ちた
出来事だった。彼が常に無表情でいてクールとされ、近寄りがたい雰囲気を
醸し出していたのは、早すぎた死を含め、父親が彼に残していった数々の罪が、
融に重くのしかかっていたからからだろう。その現実を完全に理解する間もなく
時が経ち、記憶の影が彼の心の成長に追いつくはずもなく、父親の死は
融の心の中にぽっかりと空いた大きな穴となり、触れられることなく
置き去りにされてきた。
だが、ありのままに綴られた二人の大きな苦悩は、願ってもないかたちで
歩行祭を境に一変する。忍は今ある雑音に目を向けるよう融に告げ、杏奈は
貴子におまじないをかけていた。融と貴子を取り巻く環境こそが、二人を支える
重要な役割を果し、彼らにとって思いがけないプレゼントをすることとなる。
すべてが終わり、また新たなページがめくられた二人の今後は私たちには
計り知る事が出来ないが、おそらく、また新たな苦悩と葛藤を繰り返し、
一歩進んでは一歩下がる関係性を保ち続けていくことだろう。許すということを
一度、感覚として味わった者は、この先どんな事が起ころうとも、記憶を
たどり互いを支え合っては、また新たなページをめくりつづけてゆくのだろう。
完走し、一歩近づいた融と貴子の清清しい様子には、みずみずしい生命力が
みなぎっていた。彼らの苦悩は、私たちの人生そのものでもあり、実はこの二人は、
混沌とした雑念の中、もがき生きる私たち自身であった。傷つき、哀しみ、
憎しみあって生きている私たちにとって、時は最大の敵であり、最高の味方である。
各々が心の中に何かしらの不安を抱き、良い知らせが自分のところに
巡ってくるよう祈っている。人間のエゴは深く根を張り、絡まりあって、
分かり合うはずのない互いの気持ちを交錯させる。ある人は突然の悲しみに絶望し、
ある人は願ってもない幸運に手を合わす。晴れていたかと思えば、雲が現れ
雨が降り、熱で湿気を帯びていたかと思えば、風がすべてをふきさらす。
私たちをとりまく環境は常にめまぐるしく変化を遂げている。不変なものなど、
何一つない。無常というこの宇宙の当たり前の現象に、普段なかなか実感が
もてないのは、私たちがあまりにも自分のことばかりにとらわれ、先を急いで
走ってばかりいるからだろう。気が付かないというより、わざと
気が付かないようにしているのかも知れない。形のない何かがひょっこりと
やってきては、これまでの単調な流れを変化させ、私たちを日常から
非日常の世界へと連れ去ってしまう。積み木が崩れるかのように、
バランス感覚を失った私たちは、目の前に起きた出来事にただ戸惑い、
驚くことしか出来ないでいる。自分の無力さをひどく感じる瞬間だ。だが、
この繰り返しが人生なのだ。誰もが皆、そう心に言い聞かせて生きている。
願ってもないようなことは、いつか必ずやってくる。嬉しいことも、哀しいことも
すべては順繰りにまわって来て、私たちを困惑させてしまうのだ。それが何か
分からぬままに、目の前の現象を捉えきれぬまま、嵐のように過ぎ去ってから
しばらくして、ふと気付くことがある。瞬く間にやってくるこの波は、
時間が経てば、一つの出来事として受け入れられようとするが、それまでは、
一体何がどうなっているのか分からずに、時の流れの速さに恐怖すら覚えてしまう。
私たちにできることはただ一つ、すぐ傍まで差し込んでいるかもしれない
柔らかな一筋の光を信じて、時間の流れと共にあっという間に過ぎ去ってしまう
一つ一つの出来事から目を逸らさず生きてゆくということ。小鳥がさえずり、
淡紅の花びら舞う春がきたかと思えば、新緑の眩しい、夏がやってくる。
夕闇に虫の音の美しい秋が訪れたかと思えば、あっという間に白銀の雪が
降り積もる冬の世界に引き込まれる。何者かの支配する、星空のように
散りばめられた一つ一つの出来事に目を奪われていくうち、いつしか歳を重ね、
死を迎える。ゆるやかな流れに身を任せ、優しくも残酷に移ろいでゆく
季節の流れを感じ、ゆったりと歩いてゆこう。そうすれば私たちも、
融や貴子のように、すべての出来事を許し、温かいものを胸にいつも感じて、
前に進んでいけるはずだから。
|
|