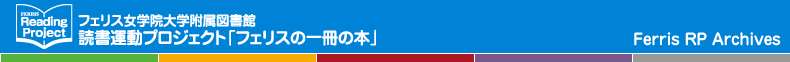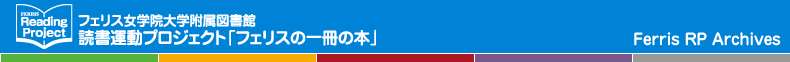|
2003年10月20日発行『読書運動通信10号掲載』記事4件中1件目
 |
 |
|
 |
| 青木淳子の〈吐息〉−『クロスファイア』、『燔祭』の宮部みゆき−
|
 |
『クロスファイア』の青木淳子は、粗末な下宿、黒い目立たない衣服、
ひっつめの髪化粧をしない素顔などで、ひときわ控えめで目立たない存在だが、
「水」のある空間を求めてさまよい続ける冒頭のシーンから、すでに印象的である。
たっぷりの水でさえあれば、蚊のわくような、沼地でもかまわない。
自宅の洗面器の水を熱湯とするだけではもはや十分とはいえなくなって、
行き場を失った力の奔逸を放ちやる場所として彼女が選んだのは、廃工場の
巨大水槽だった。水槽の水がどれほど汚れていようと、彼女には問題でない。
その全体を一瞬のうちに熱湯にすることで、あふれる力をかろうじて
無害化することだけに、彼女の関心は向けられていたからである。
力を隠し、身を潜めて、平凡な日々を淡々と生きることで、静かに
おさえつづけ、耐え続けてきた念力放火の力を久方ぶりに放ちやったのが、
アベック拉致殺人事件の加害者の青年たちであった。彼女の目の前で、
暴行の果てに、瀕死の男を遊ぶように、なぶるように(彼女の)巨大水槽に
沈めようとする青年たちの残虐な行為を、青木淳子は許せない。
彼女の髪の一振りで、青年たちは炎に包まれ、燃え尽きてしまうが、
一番端にいた主犯格の少年だけがかろうじて炎を免れ、
彼女の肩を拳銃で射撃する。
『クロスファイア』の物語は、青木淳子のやむにやまれぬ「正義感」からの炎と、
男たちの側からの反撃としての銃の炎が交錯(クロス)する物語なのである。
傷ついた肩から血を流しつつ、殺された男の恋人救出のために立ち上がり、
青年の行方を探り、恋人を探し出そうと、青木淳子は念力放火による大量殺戮を
繰り返し、ハードボイルドな戦さを孤独に戦っていく。しかし、その活劇よりも、
むしろ印象的なのは、弱々しい青木淳子の姿が垣間見られることである。
出血多量のため、途中の豆腐屋で道を聞く間に貧血し、倒れてしまって、
豆腐屋の母娘に看病されるくだりの庶民的な生活感覚は侮れない細部に満ちている。
青木淳子を駆り立ててやまない彼女の超能力の猛々しさ、選ばれた者としての
使命感と、それとはうらはらな、背負いかねる能力を負わされた者の疲労感、
脱力感、孤独な弱々しさが、ここではなまなましい実感を伴って描かれる。
かつては加害少年たちの仲間で心身に深い傷を受け、関係を断っていた豆腐屋の
娘とその母と、布団に横になった青木淳子との微妙な共感と連帯の感覚が、
警戒や自己防衛を乗り越えてさりげなく胸にしみる。
すべてを成し遂げて、恋人救出に失敗した悲しみを抱えて荒涼たる
下宿に帰り、傷の手当てもしないまま眠りにつく青木淳子のひたすらな孤独も
胸を打つ。彼女にはかつて超能力とそれを正義のために使いたいという思いを
分かってもらえると思った男がいたのだが、それは彼女の錯覚・思い込みに
過ぎなかった。そうした彼女の目の前に、超能力の持ち主が現われる。
彼女と同じように、力を持つことの孤独と苦しみと哀しみを分かりすぎるほど
分かっていた男だった。
小説の最後、彼女が唯一愛したその男、かけがえのない相手として
すべてを許した相手木戸浩一に撃たれて横たわる青木淳子には、豆腐屋で
横になっていた時と同じような無力感が漂っている。
「最初からお前を殺すための殺し屋でしかなかった」と浩一に告げられた時、
淳子は、深く息を吐く。
−−星空に向かって、淳子は呼気を吐いた。それは白く凍り、
ひとかたまりになって 空に消えてゆく。
今のは、淳子のなかの温かな“恋”だ。ああ、もうみえなくなってしまった。−−
淳子の息はこれまで相手を焼き殺してしまいかねない激しい武器だった。
しかし、今ここで雪の中に横たわり、殺されようとしながら、
まだ、淳子は相手を憎むことができない。白くかたまり、
空に消えてゆくようなため息をつくのみで、念力放火を放つための
激しい憎悪を駆り立てることはできない。
木戸浩一は、実は、彼女を抹殺するためにガーディアン
(「正義」を実行するために私刑を行うことを辞さない秘密組織)から
派遣された男で、あまりに派手な活躍を見せる青木淳子を抹殺して
組織に対する世間の関心をそらそうとするのが目的だった。
彼女を河口湖の別荘に誘い、彼女の念力放火の力を奪うように、
雪の中で狙撃したのである。残された力を振り絞って男を攻撃しようにも、
大量出血した淳子に、男の位置を確認するための、
身を起こす力さえ残されてはいない。無力化された青木淳子の痛々しいような
弱さが強調される。ここまで裏切られても、男を憎みきれない青木淳子の
女としての哀れさが凍りつくような雪のなかに、むなしく放散される
−−淳子はまた目をつぶった。声の聞こえてくる方向に神経を集中することで、
ニ人のいる場所を探るつもりだったが、目尻から涙が流れるのを感じると、
あたし、本当はただ泣きたいだけなのかもしれないと思った。−−
相手を焼き殺すべく、相手の位置を耳で測りながら、淳子はとめどなく
流れる涙にそのまま身を任したくなる。ここまで愛して、こうまで無惨に
裏切られた自分を哀れむ自己憐憫の涙だ。涙におぼれている限り彼女に
浩一は殺せない。瀕死の淳子がどのようにして、その脱力から抜け出し、
最後の結末を迎えるかは、お読みいただくしかないが、雪の冷たさの中の
激しい炎の奔出があわれで、美しい。
この青木淳子が最初に登場したのが、短編『燔祭』で、勤め先の同僚
多田一樹の妹が無残に弄ばれて殺され、その犯人らしき人々がほぼ
特定されているのに、処罰されないでいるのを見かねた淳子は、自分を
「装填された武器」として使ってほしいと多田一樹に提案する。
犯人憎しの思いに凝り固まっていた多田は一旦は淳子の提案を受け入れるが、
その念力放火をしようとしている現場に居合わせて、尻込みして、引き返し、
淳子との関係も絶ってしまう。しかし、淳子の方は犯人の処刑にこだわり、
数年後、ついに行方をつきとめて、同乗者ごと車を焼き捨てる。
新聞でニュースを知った多田は、これは淳子のしわざに違いないと、
その足取りを追いかけ、ついに疲れて家に戻ると、窓際に置いた、
妹の形見のろうそくが燃えていた。淳子がつけたのだ。そうに違いないと
外に飛び出した一樹に淳子の姿は見えず、ただ、雨の中、
靄のようなものが立ち込めているだけだった。
−−雨のなか。立ち昇る水蒸気。
目をこらすと、そのなかに淳子が立っていた。
(略)「新聞を見ててくれて、ありがとう」
ささやくような声が、今は乳白色となり、淳子の姿を覆い隠してしまった
靄の向こう側から聞こえてきた。
「さよなら、ね」
一樹は前に飛び出した。が、靄のなかに腕をさしのべても、
そこには誰もいなかった。熱い蒸気が身体を包み込んだだけだった。−−
熱い蒸気とは、満たされない淳子の吐息に他ならない。分かってもらえない
孤独を抱えたまま、雨の中にたちすくみ、ろうそくに火をともすことでしか
思いを吐露できない淳子の哀れさが際立つ、印象深い短編であった。
雪の中に倒れた淳子の吐息、雨の中、一樹に別れを告げに来た時の暑い
靄のようなため息、この2つは青木淳子という控えめで、激しい女の情念を、
せつなく語りかける媒体となっている。
この2作は宮部みゆきの数多い作品の中で、例外的な恋物語で、
分かり合えない男女のすれ違い、または分かり過ぎて続けられない恋が
哀切であった。2作とも、恋の舞台がいずれも「パラレル」という名の
カフェバーであることも、ニ人の男女の平行して交われない
恋の行方を暗示していよう。
(日本文学科教授 三田村雅子)
|
|