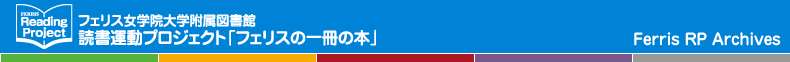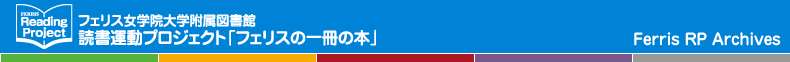|
 |
| ■
2004年度23-3・特集3.三田村雅子先生特別寄稿「冬の終わりに」 |
 |
 |
2005年3月2日発行読書運動通信23号掲載記事5件中3件目
特集:1.私たちの<今>を読むアンケート結果発表Part2
2.特別寄稿三田村雅子先生「冬のおわりに」
お知らせ:1.2005年度の活動について/2.アンケート結果と集書方針について
 |
 |
|
 |
三月になったのに、まだ寒い日が続いています。
日本海側は相変わらず大雪が続いているようです。
北海道も東北もかつてない大雪だそうです。
お里がそちらの方々、お見舞い申し上げます。
この「なごり雪」に寄せて、最近読んで胸に沁みるものがあった
二冊の本を紹介したくなりました。
一冊は去年の十二月に出たユベール・マンガレリの『おわりの雪』(白水社)、
もう一冊はアリステア・マクラウドの『冬の犬』(新潮クレスト・ブックス)。
これは去年の一月に出ました。
マンガレリの本はちょうど今頃の雪が溶け始めるころに、
長く病床にあった父を亡くした少年の物語です。
少年は古道具屋の店先に鳥籠にいれられたトビを見つけ、
どうしても自分のものにしたいと必死でアルバイトします。
養老院の老人たちの散歩のお伴をしながら、
少しずつお金を貯めてトビを手に入れようと、毎日努力しますが、
やがて雪が降り出し、老人たちは庭に出てこなくなってしまいます。
トビに魅せられた少年はそのトビを捕まえるありさまを想像のなかで、
反復し、やがて、病床の父にも捉えた人から聞いた話だと言って、
トビを捉える場面を語って聞かせるようになります。
父はその話が嘘だとすぐに見抜いたようですが、そうは言わず、
その話は気に入ったと答えます。
それほど少年の空想は鮮やかな羽ばたきと臨場感に満ちていたのです。
それから、ことあるごとに、この父子はトビ取りの話を繰り返し、
少年の語り口は洗練の度を加えていきます。
嵐の夜に雨の音をかき消すように語られたスリリングな語りから、
静かに淡々と語られる時まで、変奏を重ねつつ、
少年の嘘は二人だけに所有される大事な物語として
二人をつなぐ絆となってゆくのです。
その間にもトビへの熱に取り憑かれた少年はアルバイト代の不足を補うべく、
子猫を殺す仕事を引き受け、犬を殺す仕事を引き受けます。
でもその犬は少年の大好きだったおばあさんの愛犬で、
おばあさんが亡くなった後、息子からその処分を大金で依頼されたのです。
トビに目が眩んだ少年はトビを手に入れるために、
殺したくもない老犬を処分する仕事を引き受けてしまいます。
実を言うとこの小説は、少年が朝早く犬を連れて雪の上をどこまでもどこまでも
歩いていき、午前一時にようやく帰ってきたその長い道のりの往復の場面を
最大の見せ場としています。
少年を信じ、歩みを共にし、疲れてもあるきつづけ、
どこまでも、信じ、従ってきた犬の呼吸・かすかな聞こえないような足音。
そして二人の「散歩」が、どうなったのかは、じかに読んで、
体験してもらうしかないのですが、その昼と夜の場面は、長い長い、
息を詰めるような緊迫の場面として描かれています。
そして、念願のトビを手に入れた少年は、
それ以来罪意識で眠れない夜を過ごしながら、
トビへの熱狂を末期の父と共有していきます。
父の死で終わるこの小説は、父の揺るぎない支持によって、
この少年がフィクションの「語り手」として、
「書き手」として出発していくであろうことを予感させます。
父が危篤に陥り、意識を無くなす前夜、
少年は「やってみるよ。駅と国道との道のり、たどってみる」と決意します。
犬との最後のつらい道行きのことです。「道を辿り直す」とは、
いままさにここに書かれているような、告白を書く決意に他なりません。
トビ欲しさに目を眩まされ、深く覗きこむことのなかった、
みずからの罪意識を、ここで語り手の少年は雪に閉ざされた池の青さを
のぞき込んだように、振り返ろうとしているのです。
周囲では雪の季節が終わりかけて、緩んだ雪が溶け、熱い日差しがさしてきます。
そうした、肌に感じられるような触覚・かすかな音を聞きつける聴覚、
光りの揺らぎを敏感に受け止める視覚といった感覚の一つ一つが丁寧に配置され、
ひそやかに網目をなしてこの小説は構築されてゆくのです。
表題となった「おわりの雪」は季節の移り変わりを示すばかりでなく、
父の最後の「雪」、主人公の少年時代の最後の「雪」、
書き手として出発する契機となった「雪」を示しています。
雪とその溶ける水滴の音(尿に濡れ凍り付いていた少年のズボンの水の滴り、
水道の水の滴り)の通奏低音のような繰り返しの中に、
この小説は家族・死・罪という重たい問題を、どこまでも静かに、
しみ通るように、抱え続け、反芻し、問いかける物語として姿を表しているのです。
「この小説を読んで泣きました」というのが、
宣伝文句となっている小説は衢に氾濫していますが、
このマンガレリの『おわりの雪』は「泣く」というよりも、
ギュッと胸が絞られるような息苦しい苦悩が、甘美な想い出に溶け込んでいく、
そのあやうい一点で踏みとどまった、厳しくも美しい回想の物語だと思われました。
装幀も表題の文字も作品の世界を控え目に示唆して印象的でした。
犬と家族と雪の物語というと、カナダの作家アリステア・マクラウドの
きらめくような短編小説を忘れることはできません。
アリステア・マクラウドはプリンス・エドワード島の隣の島
ケープ・ブレナンを舞台にした少年時代の回想の物語を書き続けている
寡作の作家ですが、その邦訳された短編集『灰色の輝ける贈り物』
(新潮クレスト・ブックス)『冬の犬』(同)の二作は、
家族の強い絆と、動物の信頼と愛、それへの裏切りを描いて、
すべてすばらしい出来です。
寒さの厳しさ、貧しさの極まりを描く点も、マンガレリとおなじですが、
マクラウドの小説は自然がもっと厳しく、動物への思いももっと
激しいものがあります。
動物のなま暖かい血が匂い立ってくるような激しさと、
それを包む自然の厳しさが、そうでしかありえなかった
人生の「選択」の意味をつきつけてくるような小説です。
これも是非読んでいただきたい切ない傑作でした。
どちらがいいというわけではありませんが、私はマンガレリを読んで、
マクラウドを思い出し、マクラウドを読んで、またマンガレリに立ち戻りました。
マンガレリは繊細でしなやか、マクラウドは剛毅にして潔癖な印象があります。
両者とも、淡々と、しかし、私たちを静かに揺すぶって放さない
回想の物語を物語って、名手中の名手なのだと思わせられます。
心を洗いたい、と思うような日々に生きなずむあなたに、
お薦めしたい二冊の本でした。
(文学部教授 三田村雅子)
|
|