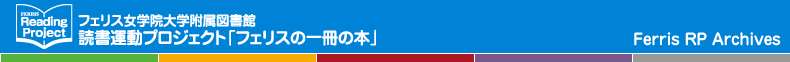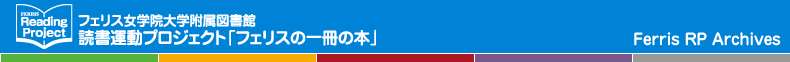|
2003年9月30日発行『読書運動通信9号』掲載記事3件中2件目
 |
 |
|
 |
| 時を越え、「壁」を越え―富岡多恵子『水上庭園』―
|
 |
『水上庭園』は、1970年から90年のベルリンの壁崩壊に至るまでの、
日本人女性で詩人を職業とする「わたし」と、Eというドイツ人男性の、
20年にわたる魂の交感とその軌跡を描いた作品である。冒頭では88年の
東京を舞台としつつ、「わたし」がEと再会するところから始まる。
再会の感慨をあえて外に表さない「わたし」は、その代わりに18年前の
Eの手紙を改めて読み返す。2人が知り合ったのは、シベリア鉄道の列車の
中である「わたし」は34歳、Eは21歳だった。Eは一人で旅行していたが、
「わたし」は夫同伴であった。当時のEからの手紙には、若者特有の
夢見がちなその文章の中に、「わたし」への一途な思いがちらちらと
熱っぽく告白されている。過去と未来が「わたし」の中で同時に交錯
していく媒体として、手紙は重要な役割を担っている。
ドイツ語講師の職探しのために来日し、「わたし」にも斡旋をあてにする
眼前のEは、しかし、若い頃のひたむきさばかりではなかった。やがて彼は、
いつまでたっても自分の職が見つからないことに苛立ちをおぼえ、東京に
見切りをつけ、「わたし」からも去って行く。そしてその2年後の90年、
今度は「わたし」がEに会うためにドイツへ行く。「わたし」が夫の承諾の
もとにドイツへ向かった目的は、Eに会うことの他に、既に崩壊したベルリン
の「壁」の跡を見ることにあった。
表題の「水上庭園」とは、タイの「水上生活者」の住処をイメージしつつ
Eが描いた「舟」の絵に由来する。その「舟」は、ボートが2隻並んでつながれ、
その上に屋根のついていた。Eはこのような「舟」を作り、またそこで暮らす
ことを夢想する。
つながれたまま2つ並んだ「舟」は、1つはE自身を、もう1つは、恐らく
「わたし」を暗示しているにちがいない。「水上庭園」とは、定住を拒否するEの、
自分が浮かんでいるような感覚を投影させるとともに、「わたし」だけと固く
結ばれたまま、いつまでも一緒に漂っていたいという願望を具現しているのである。
そのEの漂流願望を描いた「舟」の絵の意味に、「わたし」は深く立ち入ろう
としない。夫がいながらEとも関わり続ける「わたし」は、彼を高揚させて
実は密かに楽しんでもいたのであり、「わたし」の女性としてのずるさが
ほの見えている。既婚者の日本人女性が西洋の男性に慕われるという設定が、
ここで重い意味をもって現前する。
『水上庭園』は、西洋文化が優位で日本は劣っているという、日本人に
潜在する西洋への先入観をくすぐるようにして、「わたし」とEの背徳的な
関係を語る。「わたし」はEに、「Eといっしょに暮らさなかったのは、
わたしが日本人だったからだ。私は日本語で暮らして日本語でなにかを
書かねばならなかったのだ」と英語で告白する(言語の違う彼らは英語を
共通語にしているが、互いに母国語以外の言葉を用いるという設定は、
意思の疎通の不自由さを意味しており、重要である)。13年歳下の
西洋人男性から熱愛されることの恍惚に溺れたいと密かに渇望しつつも、
そうした陶酔をもってしてもなお、「わたし」は、「日本人」・「日本語」
に対する強烈な帰属意識と自己同一性を捨て去ることができない。
そしてさらに、「日本語で書く」ということの意味は、次のように
捉え返されている。
(詩を書くことを)「生きるため」といわず、露骨にも「食べるため」
と(人々に)いったのは、詩を書くことがどこかで自己治療でもあったのを
かくすためです。自分が病者だというのがいやだからです。
書くことへの強烈な欲求の中に、自己自身の「病」をみとめずには
いられない「わたし」もまた、Eと同様に孤独であり、迷いの中で
生を模索していた。「わたし」のEへの共鳴は、自分を「病者」とする
意識の上にある。
20年にわたる「わたし」とEの関係とは、一体何だったのだろうか。
「わたし」とEとの間には、国境、文化、言語、年齢、人種、男女差といった
あらゆる「差」が剥き出しにされている。『水上庭園』の語り方自体が、偏見や
先入観から産み出されたさまざまな差異に対して敏感であり、挑戦的であると
いっても差し支えない。恐らくドイツに来た「わたし」が、42歳になっても
時間給で低所得のEを欠勤させてまで同伴をしいるほどに執拗に拘泥した「壁」は、
単に社会情勢の変動の中だけで捉えられているのではなく、彼らの間にまたがる
幾つもの層をなす分水嶺そのものを象徴しているのであり、そこには越えがたい
断絶を十分に認めつつも、人間として平等に触れ合いたいという、「わたし」の
願いが投影されているのである。
『水上庭園』の特徴は、女性の業の深さのようなものを、そのような国境的な
「差」において捉え返そうとしたところにある。
しかし、東京でぎこちなく別れた「わたし」とEは、ドイツで再会した時は
互いに心を開き、絆を改めて確かめ合っている。
「忘れないで」とEがいいます。…わたしも鸚鵡のように同じことをいい、
Eとわたしは「忘れない」とまた鸚鵡のようにくり返します。いったいなにを
忘れなかったか、20年後にふたりにたずねてみたい気がします。
「わたし」が独りで帰国するところでこの小説は終わっている。
「わたし」とEは「夫婦」や「友人」といった、社会的な関係とは無縁なところ
にあった。けれども、そのような規定不能の関係が、決して気まぐれな出来心で
成立した安易な結び付きではなかったことが最後には読者に了解されていく。
思いを同じくし、精神的に深く結ばれている者同士でありながら、現実の中では
一人一人で生きて行かなければいけない愛別離苦がそこには描かれているのである。
そして、別れて生きる時も、その延長に「20年」という厚い時間が、今度は未来に
向けて力強く重ね直されていくのであり、終わるけれども終わらない物語である
ことが、現在形を主体とする流動的な文体のうちに透視されていく。のみならず、
年月を経てもなお風化せずに残り続ける思いが存在するのだということを読者に
教えてくれているという意味で、読むことそのものの浄化作用も同時にもたらされ
ているのである。
私が『水上庭園』を手にしたのは、26歳の夏であるが、本はフェリスの図書館で
見つけた。その時大学院生だった私は、格別富岡多恵子を愛読していたわけでは
なかったが、時間と空間を縦横に切り裂き、それをモザイクのように組み替え
ながら物語が展開されていくのが小説として新鮮であるのと、みずみずしい文体に
鮮烈な魅力を感じ、1日で読み終わってしまった。「わたし」という1人称形式、
容姿を具体的に描かない手法がまた、読者の自己投影をさせやすくしていた。
「書く」ことそのものに迷いを抱く「わたし」に、論文の低迷にあえぐ
自分自身が、その時はおのずとなぞらえられたのである。
今でもときどき、何に対しても興味が持てなくなったり、結局自分は
怠けているのではないかという感覚にとらわれると、『水上庭園』の
世界を思い出す。「舟」を妄想するEと、「壁」の消えたベルリンに、
一個人としての自分の魂の解放と再生を祈念する「わたし」の無垢な姿が
よみがえるのである。本を読むことは、決して時間の無駄ではないことを、
フェリスの後輩のみなさんにも知っていただきたいと思います。
(非常勤講師 石阪晶子)
|
|