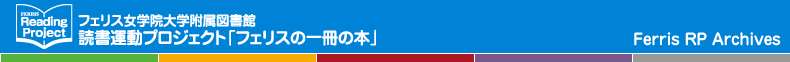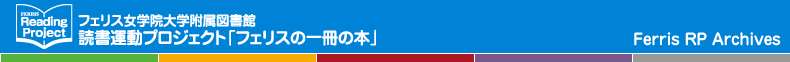|
 |
| ■
01-4・私と宮部みゆき この世に「たった一人」のひと |
 |
 |
2003年4月8日発行『読書運動通信1号』掲載記事4件中4件目
 |
 |
|
 |
宮部みゆきという作家を私が初めて知ったのは、1990年、山口智子が
主演で放送された「魔術はささやく」を見た日である。それを見たあと、
母に宮部氏の小説「パーフェクト・ブルー」を薦められて読んだのが、
文章として宮部みゆきに触れた初めだったように思う。結局読んだのは11・12歳。
ちょうど10年ちょっと前というわけだ。意外と長い付き合いなのか、短いのか。
それ以来、宮部氏のファンである。
私は宮部氏の長編小説を読むのが好きだ。まるで別の場所で発生した
様々な事件や、関係ないはずだった人々が、1つのところに集結していく。
事件を説明していく。関係ないかのように始まった物語を、
上手くつなぎ合わせていくのが本当に上手い。まるでパズルのピースを
はめるように、綺麗に最後は繋がるから、安心出来る。
読後感が抜群に良い作品を書く作家だ。そう言った気持ちのいい読後感が楽しいし、
何より読みやすい。時折、読みやすいと言うこと=稚拙・低年齢向けと考える人を
見掛けるが、エンターテイメントとしての小説の読みやすさは、
魅力の1つだと思っている。また、本当に力量のある作家というのは、
些細な言い回しやプロットの巧さが秀でている作家なのではないだろうか。
難しい熟語や漢字や、観念的な文章を垂れ流して、読む側に何の感情も
湧き起こさせない小説は、少なくともエンターテイメントではない、
と私は考えている。その意味で、宮部氏は極上のエンターテイナーな作家だと思う。
彼女の小説は、読んだ後、まるでパズルを完成させたかのような爽快感を
感じることが少なくないからだ。面白いと、素直に感じるからである。
ここで私が挙げたいのは、宮部氏の短編小説「たった一人」(「とり残されて」)
である。この作品が収録された短編集「とり残されて」は、ちょっと不思議な話で
纏められた1冊である。要するに、多少娯楽性が強いというか、
大人には受け付けにくい類のものであろう。『火車』のように硬派な小説ではなく、
短編なのでさくさくとテンポよく読める。評価は年代・好みによって
分かれるであろう。しかし、まず読んで驚いたのが、主人公が冒頭で
探偵社を訪れ依頼することが、「自分の夢に登場する風景を探して欲しい」
と言うことなのである。「毎晩、夢をみるんです。その夢のなかに、
いつも同じ場所が出てくるんです。わたしが行ったことのない……
知らない土地なんですけど、でも、どこか懐かしいような気もするの。
それで、どうしてももう1度そこへ行かなくちゃならないような気もしてくるの」
この台詞で、既にこの小説の評価は、私の中では決まってしまっていたような
気がする。特別おかしな言い回しではないし、心に残る感動的な台詞でもない。
だが、主人公が夢に見る場所に、行かなくてはいけないような気がしている、
と言う何か神秘的とも言える設定が、私を殊の外ワクワクさせたのは事実だ。
不可思議な小説を読むにしても、もう、オカルトを信じる気持ちや
少女らしい気持ちを、ばさっと捨て去ってしまっていた頃ではあったが。
それだけの魅力が、この小説にはあったのであろう。
「たった一人」は、一見シンプルで、格好良くもないタイトルだ。
京極夏彦氏や島田荘司氏の小説のタイトルのように、見ただけで
想像できそうなタイトルではない。シンプルすぎて、イメージが
特定できないタイトル。この「たった一人」がどうして「たった一人」なのか。
元々、主人公は「学校を出て、あたりまえのコースで就職し、
決まった時刻に出勤して、決められた時刻に退社する。そういう毎日だ。
これという変化もない。それでいて彼女は、この暮らしに、平凡だと言い切って
安心していられるだけの安定感も感じてはいなかった。いつも何か不安で、
不満足で、渡されていないおつりがあるような気がする」と表現される
永井梨恵子という若い女性。そうして「少し白髪が目立つ」「目尻と口の端に
深いしわのある」40歳ぐらいの中年男で、「席につくとき、相手に正対せず、
少し角度をつけて座る」と表現される、探偵の河野。薄暗い探偵社で、
何処にでもいそうな若い女性と、少々古ぼけた感じの探偵の、2人の出会いから、
この物語は始まる。
2人で始まる物語だが、最初、河野は夢の場所を探すお嬢さんの依頼に、
乗り気にはならない。確かに、そんなことを言う若い女性が尋ねてきたら、
まず「精神病院の場所を知っているか」と言ってやりたい。
正気で夢にでてくる場所を探そうだなんて、普通は考えないはずである。
実在するのかどうかも判らない景色。途方もない捜し物だ。しかしまた、
梨恵子も諦めずに河野に縋り付き、必死に探し出そうとする。
探偵社を訪ねる人間とは、ある程度の覚悟をしてドアを開けるものなのであろう。
そんな、少々不協和音で始まる「2人」の小説のタイトルがなぜ「1人」なのか。
それは、推して知るべし、であるとも言える。だが、シンプルだからこそ、
隠された意味を問う事も出来るのではないだろうか。
ここで皆まで言って良いのかどうか、甚だ疑問なので、
あまり深く語ることは出来ないが、「2は割れば1だし」などと
訳の分からない言葉でお茶を濁してみる。
2人が遭遇する、不可思議な体験。宮部みゆき独特の現実と非現実の
交錯する世界観。その不思議自体を話してしまえば、
この小説は面白くなくなってしまうので、ここでは語らないでおく。
読んで、確認して戴きたい。2人が探し出そうとする景色は、
一体なにを意味するのか。なぜ探そうとするのか。
そうして、ラストシーンで1人で歩き出し、何かを決意する梨恵子に、
何を感じるのだろうか。何かを探しているような終わり方が、
非常に「とり残されて」と似ているのだが、ぞっとする印象の
「とり残されて」に比べ、梨恵子の願いのようなものが感じられて、私は好きだ。
いつでも必死に前を向いている、梨恵子の姿勢が好きだ。
梨恵子が望むものを探し出すことが出来ることを祈る。
(卒業生 田邉愛美)
|
|