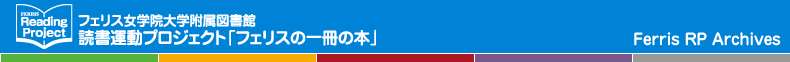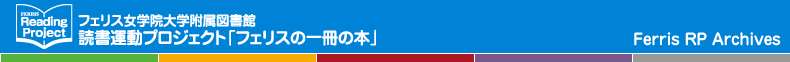|
2003年6月19日発行『読書運動通信5号』掲載記事4件中2件目
 |
 |
|
 |
高野文子さんという不思議な漫画家がいて、『黄色い本』という
素敵な本を出したのをご存知ですか。今年度の手塚治虫漫画大賞の
受賞作ですから、名前だけは御覧になった方も多いでしょう。
もしまだ御覧になっていないのなら、ぜひ手に取ってみてください。
本を読むことの苦しいような陶酔の時間の持続を、平凡な日常の時間の
中に織り込みながら、ここまで見事に描いた作品を私は知りません。
田舎の比較的貧しい家に育った少女が高校を卒業し、メリヤス工場に
就職するまでの半年間を、1冊の本を読む時間として描いた作品です。
学校の勉強・家の仕事や、家族の面倒を見る合間に、時間を盗み取るように、
ひたすらマルタン・デュガールの『チボー家の人々』を読みふけり、
日常の他愛ない繰り返しの時間を生きると同時に、小説の中の人々とともに
革命の情熱を語り合い、世界を相手取って考えを深め、恋愛にも友情にも目覚めて、
生きようとする姿を、淡々と、しかし大胆に描いた70ページの小さな「大作」です。
少女はジャック・チボーの友人に宛てた手紙を読みながら、「命をかけて、
君のものなる」という結びの言葉を、暗闇の中で悶えるように反芻します。
あたかも自分自身に贈られた言葉であるかのように。
雪の中独りで小学校にシャベルを取りに行った少女は、雪の上に残された
足跡の上に、革命に向かって立ち上がろうとした人々の雑踏を幻視します。
ジャックが掴んでいた同志の娘の腕は、ひりつくような熱さで雪の中を歩く
少女にも追体験されます。少女がシャベルを担ぎながら、あたかも銃を担いだ
人々のように、高まる胸の鼓動を抑えて、たった1人の「行進」をする場面は、
冷たい雪の中に、渦巻く興奮と熱気を伝えるものでした。
ジャックの乗った飛行機が墜落する場面では、本のページに顔を埋めて衝撃と
悲嘆に耐えているかのようです。墜落したジャックの体が草の上で焼け尽きよう
としている時の熱と匂いを、炬燵に横になった少女はみずから感じてさえいます。
実はその炬燵には、少女の幼い従妹の毛糸のパンツが干されていたのですから、
従妹の漏らしたおしっこの匂いも炬燵の中には当然漂っていたに違いありません。
おしっこの匂いがジャックの肉の焦げる匂いにも重ねられてしまうという、
主観と客観の混交によって描かれる滑稽にして哀切なジャックとの別れでした。
日常そのものの平凡な時間が、いつでも熱に浮かされたような興奮の
時間に変転しうるという読書の目くるめく逆説と陶酔を、この漫画は
語りかけてやみません。やがて雪解けが始まり、就職も決まり、借りていた
図書室の本を返す時がやってきます。「ザッ」、「タク・・・タク・・・」、
「サー」と繰り返される雪解けのしたたりの音が幸福な夢見る読書の時間の
終わりを刻んでいきます。雪解けと春の訪れとともに、現実に立ち向かい、
働かなければならない時間が迫っているからです。せかすように、
この一瞬一瞬の貴重さを印象づけるように、雪解けの音は続きます。
窓の向こうの雪解けのしたたりは、読書への耽溺に別れを告げていく
少女の涙のようです。
本の最終ページを、すっかり雪の解けた屋根の上で日向ぼっこをしながら
読み終わる少女の耳には羽虫のブブブというかすかなうなりが聞こえ、
その小さな影がページに映っています。本を丸ごと読みきったという
充足の思いがそのやわらかな響きのなかに静かに広がってきます。
本を所有することよりも、本を読むことに全身全霊をかけた日々の積み重ねが
そこには語られているのです。
少女は学校の図書室の本棚に本を返しますが、返された本は、彼女の名残惜しい
思いによって、薄く光を放っています。いつでも戻っていくことのできる、記憶の
中の黄金の本棚に本を返していくこの読書の終わりの静謐な場面が
私は1番好きです。胸が締め付けられるような少女という時期への感傷と、
それを見据える冷静にして揺るぎないまなざしとによって紡ぎ出された
稀有の作品だと思われました。
読書の意味について、問われた時、私はまずこの本のメッセージを思い浮かべ、
そのすばらしさを読書に夢中なすべての文学少女たちと共有したくなりました。
私にとっての読書も、作品に浸りつつ過ごした長い時間だったことがありありと
思い出されます。源氏物語はもとより、『カラマゾフの兄弟』、『紅楼夢』、
『戦争と平和』、『赤と黒』、『ブッデンブローク家の人々』、『ローマ帝国
衰亡史』など、好んで長い物語を読みふけり、現実の生活よりもはるかに
生き生きと、小説の中の時間を生きていました。受験勉強からの逃避も
あったのでしょう、ちゃんと勉強しているか絶えず確認に来る母
(わたしの母は大変な教育ママだったのです)の目を盗んで、来る日も来る日も
源氏物語を盗み読みしていた時代の熱意には到底及びませんが、今こうして
源氏物語や枕草子を研究などしているのも、そのころの盲目的な狂熱の余韻である
に違いありません。
本を読むのが誰よりも好きで、職業としても、趣味としても、本を読み続けて
来て、最近痛切に感じているのは、年々小説が読めなくなってきたということです。
虚構の世界に入っていくのが億劫で、つい知識や、考え方を学ぶ本に興味が
移ってしまいがちです。私はかなり努力して、新しい小説に挑戦している方
ですが、それでもやはりかつてのようには小説に心が向きません。
『黄色い本』の世界のように、虚構の世界に遊ぶことのできる期間は短い
のかもしれないと思います。
まだ自分が何者になるかも知らず、ひたすらまどい続けた青春時代に、
飢えるように小説に人生の意味を求めていたその激しさは、今の私にはありません。
小説は中学・高校・大学という人生のある時期に出会わなくては、もう一生出会う
ことのないジャンルなのかもしれません。自分の小さい世界から抜け出して、
自分をみつめることができるという体験は、人生のある時期にもっとも必要とされ、
豊かに開かれてくるものなのでしょう。
その貴重な時期に、小説に出会えない人が今急速に増えているようです。
1ヶ月に1冊も本を読まない高校生が67%にも及んだというのは1昨年の報告ですが、
今や、日本は先進国の中で、もっとも本を読まない国となりつつあります。
私が高校生だったころ、『黄色い本』の世界はそれより数年後ですが、
日本の高校生も大学生も大人も実によく本を読んでいました。その文化が空洞化し、
崩壊しようとしている現在、本に変わる新しい文化の公共性を生み出すものは
まだでてきていません。本によって、虚構によって、人生の「意味」を
ひとまとまりのものとして把握する力が衰えてしまっているのではないか
と不安になります。
こうした時代ですから、自分が平安文学の専門家だから、平安文学だけを
やっていればいいとは到底思えなくて、私は読書運動をさまざまなかたちで
展開しようとしているのです。宮部みゆきを読むプロジェクトの一方で
展開している朗読の運動も、作品を読む時間と聞く時間を一致させられる
稀有の時間として大切にしています。もう1つこれは専門絡みですが、
幸田弘子さんと源氏物語の原文朗読と解説の会(全54回)を
さいたま芸術劇場で開いています。こうした試みがどれほど有効か
わかりませんが、「読書」からもらったもののいくぶんかでも、次の世代に
伝えていければと、奮戦中です。
(文学部教授 三田村雅子)
|
|