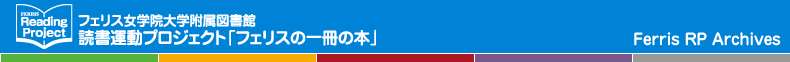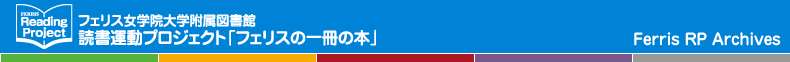|
 |
| ■
2004年度16-2・先生方の一冊〜コミュニケーション学科設立記念 諸橋先生大特集-5 |
 |
 |
2004年5月17日発行読書運動通信16号掲載記事4件中2件目
特集:先生方の一冊〜コミュニケーション学科設立記念 諸橋先生大特集!
*この記事は1-5まであります。
 |
 |
|
 |
| 村上春樹の70年代の「雰囲気」と80年代の「風」
|
 |
かつて作家は政治的なオピニオンリーダーだった。
だから高校から浪人にかけて集会や講演会で、
大江や小田などを結構見た(見に行った)ものだ。
ベ平連、革自連などの市民運動に多少かかわったこともあって
小中陽太郎や中山千夏、矢崎泰久らと一緒になることもあった
(ぼくのことは憶えていないだろうけれど)。
また、自宅近くでは現在でも黒井千次をよく見かける
(メーデー事件の後日談を扱った『五月巡歴』は、バンド時代に
好きだった子が住んでいた高円寺とおぼしき場所が出てきて、辛い作品だった)。
浪人時代、当時芥川賞を取りたての森敦や、まだ電通にいた新井満などと
テレビに出て討論したこともある。どうでもいいことだが、
スタジオで一緒になった2級下の高校生の女の子は、偶然、
当時一緒にミニコミを出していた大学生の友人の妹で、
現在彼女は博多に暮らしておりドイツ人の政治学者の夫と離婚して
NPO法人をやりながら大学の講師もしている。
お互いもうそんな年なのだ。
いずれにせよ、「生身の作家」と会うことで、
こちらも「文化度」が上がるような気がしたものだ。
そして、事実彼ら・彼女らの謦咳に接することは、やはり意義深いことでもあった。
そんなミーハー的な憧れの中、親しく話したことがある作家
(もっとも1回きりだが)として印象深いのは、井上光晴のことだ。
1981年の大学生のとき(と言ってももう20代半ばだったけれど)、
やがて市役所に就職が決まる女性、その後ぼくより遅く大学教員になる
同じ年の男性の友人Tとで、雨の山下公園・元町・山手あたりで遊んだ。
ホテルニューグランドのレストランに3人とも濡れたGパン姿だったため
入れてもらえず、高校時代から行きつけだった中華街の鴻昌という店で
飲み食いをしていた時、その頃留学先から帰ってきて国内演奏活動をしていた
新進バイオリニストの天満敦子を連れて井上光晴がその店に入ってき、
ぼくたちと席が一緒になったのだ。友人2人も文学や政治状況に造詣が深く、
文学談義(と言うより文壇ゴシップ)や政治談義に花を咲かせ、
あまつさえ彼に老酒とカニをおごってもらった。
『地の群れ』『虚構のクレーン』をはじめとする党派的小説で名を馳せ、
熱心なファンのいた作家だったが、ぼくももちろんほとんどの作品を読んでおり、
中でも『心優しき叛逆者たち』『未成年』『ファシストたちの雪』など、
不気味な管理社会を描き、人物たちが章ごとに異なる多層的な
手法の作品が好きだった。
それほどの年齢でもなかったのに井上光晴が死ぬのは、
それから何年もなかったような気がする。
また、よもやその十数年後、好きな散歩コースであった
山手のカソリック教会の裏にあるフェリスに勤めるようになるとは
思わってはいなかった(ちなみに、天満敦子もフェリスにゲストで
来てくれたことがある)。
ところでその時、ぼくたち3人は既に村上春樹を読んでいた。
村上春樹が『風の歌を聴け』で群像新人賞を受賞したのは、
ぼくが大学に1年生として入り直した1979年のことだ。
大学の図書館の『群像』で丸谷才一らの選評を読み、
単行本になってからはすぐに購入した。翌80年には
ぼくと同年齢の田中康夫が『なんとなく、クリスタル』で
文芸賞を受賞することになるが、モノの固有名詞や数値にこだわる、
「記号とのたわむれ」を臆面もなく書き連ねた小説ともいえないような小説で、
村上のそれの方は大江に似て固有名詞や数値を散りばめはするが、
あやういところで品位を保っていて好感が持てた。
翌年、社会理論ゼミの夏合宿のレジュメでは、
「みんな大嫌いよ」
「あらゆるものは通り過ぎる。誰にもそれを捉えることはできない。
/僕たちはそんな風にして生きている」
などの彼の小説のフレーズをあちこち散りばめた何十ページにものぼる
レジュメを配布しようとし、担当教員から不興をかった。
ぼくとTとは、学部生とはいえ2人ともあちこち「回り道」をしてきたため
20代半ば近くになろうとする同い年であることもあって親しかった。
やがて我われは『風の歌を聴け』の続編である『1973年のピンボール』も
リアルタイムで読み、ホテルのプールで泳ぎ、プール一杯分のビールを飲み、
日比谷公園で鳩にポップコーンをやり、ピンボールにハマり、
マイヤーズのラム酒をバーで飲みながら、「ジェイズ・バーごっこ」と称して
最近見なくなった同級生たちのことをネタにしたりしながら、会話を真似したりした。
「みんないなくなるね」
「どこかで松ぼっくりか何か食べて死んでしまったかもしれない」
「人生はこのグラスの中の氷みたいなもんだ」
「あんたは上手いことをいう」
「キザなんだ」
3人で雨の横浜に遊び、中華街で井上光晴におごってもらったの
はそんな時期だった。
英文科でヴォネガットだったかメイラーだったかミラーだったかを
卒論に選ぼうとしている(英米文学に多少詳しかったぼくと、話がよく合った)、
のちに市役所に勤めることになる女性は、ぼくとTとの
「ジェイズ・バーごっこ」を呆れて見ていたものだ。
70年代を舞台にした作品でありながら80年代の新しい“気分”を
代弁した村上春樹の「鼠とぼく」3部作(『ダンス・ダンス・ダンス』を入れると
4部作となるが)の『羊をめぐる冒険』が刊行されたのは、
ぼくとTが大学院進学を射程に入れて卒論を書いている1982年のことだ。
Tは、発売日に買って2日で読み了えていたぼくの『羊』を速攻で借りてゆき、
飲み物のしみをつけて1週間後に返してきた。
ぼくの卒論は原稿用紙に換算して600枚近く、Tの卒論は250枚近くに
なるものだった。卒論のエピグラフには、『羊』のフレーズと大江の
『雨の木を聴く女たち』を引用した。
あれから、さらに20年以上が経った。
ぼくにとってはこれらのできごとや記憶はついこの前のことのような
気がしてならない。
そして、小説とともに時代をきざむ本との蜜月は、
大体あの時期に終わったように感ずる。
それから先は、金に糸目をつけずマンガ単行本を揃え、
専門の学者として関連する学術書をほとんど全て揃え、
幾何級数的に蔵書が増えて行ったが、本フェチの性格だけが固着し、
「内容」への愛着が薄れてきたのだ。研究のプロともなると、
単行本にせよ学会誌や雑誌にせよ、まず「所有すること」が大事で、
単行本の場合はとりあえず目次とあとがきを眺めておくだけ、
雑誌の場合は誰がどんなタイトルで書いているかパラパラめくる程度で、
大体様子がわかるからである。
しかし、こういう「読み方」は不幸な読み方だ。
それとともに、ぼくにとっての「同時代」も80年代前半で終わった。
90年代はオウム真理教事件、21世紀は9・11と、作家や学者の
想像力を超えるできごとが起き、取り残された感じがしているからだ。
だからぼくにとって、本とともに時代を記憶する蜜月関係は終わったと
感じざるを得ないのだ。
これからは、そのような「時代の産物」であることを忘れて、
せっかくのこれだけの蔵書や、好きな作家を全作品揃えたのだから、
ビンボーしていた時期に1つの本を繰り返し暗記するほど読んだ
かつてのような幸福な本とのつき合いを、老後にもう1回体験したいと思っている。
それは、やっと本が「自由に読める」ということなのかもしれない。
|
|