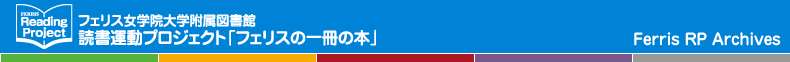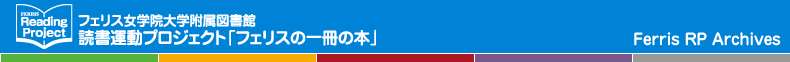|
| 読書運動プロジェクト 文学部日本文学科3年 合澤早希
|
 |
前期は、フェリス1冊の本、「アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない、
恥辱のあまり崩れ落ちたのだ」を読書会で講師を招いて皆で疑問を共有したりしました。
題名だけ聞くと、さぞかし難しい本だと思ってしまいがちですが、
モフセン・マフマルバフ氏(この本の著者)の心情、会話がふんだんに描かれているため、
そんなに難解な文章を読んでいるという感じはありませんでした。さて、肝心な
読書会の内容ですが、9・11の後、アフガニスタンという国はたびたびメディアに
登場し、人々の頭に良くないイメージを植え付けてしまった気がします。読書会では、
アフガニスタンの気候、民族、文化などを本の中から探ることで、新しいイメージを
もらうことができました。それは、綺麗な青い空であったり、クルド民族であったりと、
良くないイメージを覆すようなものばかりでした。綺麗な青い空は日本もアフガニスタンも
同じです。しかし、同じ空の下で起こっていることも忘れてはいけません。
苦しむ人々がこの1冊の本に、そしてアフガニスタン国内にたくさん存在する
ということを覚えていること、アフガニスタンの現状(良いところも、悪いところも)を
多くの人に知ってもらうことこそ、モフセン・マフマルバフ氏が願っていること
なのではないでしょうか。
後期は、前期と一転して「読書会」という名前そのままに各自が持ち寄った本を
紹介する形で進行しました。人というものはおもしろいもので、示し合わせていない
にも関わらず誰一人として重なって本を持ってきてしまうことはありませんでした。
私が紹介したのは宮沢賢治の短編「ツエねずみ」ですが、よほど印象が強かったのか、
今も読書会の話になると、「あなたが紹介したツエねずみは・・・」と引き合いに
出されることも。(笑)本というのは1回しか読んだことがなくても、覚えている
ことができる媒体であると思います。また自分の好きな本を紹介することで人から
思いもよらない新しい発見があることも確かです。後期の「読書会」は1回参加でも
気軽に参加できることもあってか、参加者が多く活気がありました。
|
|