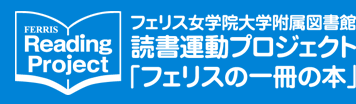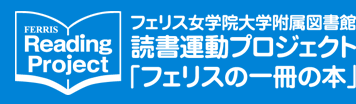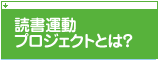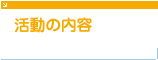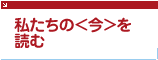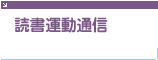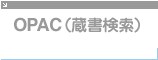|
● はじめに ●
このたび、文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム」に採択された本学の「読書運動プロジェクト」は、シカゴ市で大きな成果を上げた「一冊の本を読む」プロジェクトに触発されてスタートしました。
2002年度より始まったこの活動は、毎年度のテーマに対し、さまざまな角度からアプローチし、講演会をはじめとする諸企画によって関心を高め、読書へ引きつけようとするものです。当初より学生ボランティアメンバーを中心として、学生の企画提案について教員が助言し、職員が事務的なバックアップをするという、全学的な体制で運営し、更なる拡充を続けております。
1年目は、モフセン・マフマルバフ監督の『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない 恥辱のあまり崩れ落ちたのだ』を取り上げ、読書会、関連映画上映会、関連講演会、演奏会を開催しました。
2年目は「宮部みゆき〜ミステリーの中の<社会>と<時代>を読む」をテーマに、3年目は「等身大の自分を探す」と題し村上春樹を読み、4年目の2005年は「ファンタジーを読む」と展開しました。その内容を受け、2006年度のテーマは数あるファンタジー作品の中から宮沢賢治の作品にスポットを当てて、より深く探求していきます。
これまでの活動の中で、2003年度は、「私たちが学びたいこと」という学生提案型の授業で、読書運動プロジェクトのテーマである宮部みゆきを取り上げ、プロジェクトと授業との連動を図りました。
その成果は、学生主体の150ページにわたる論文集の発行という形で結実しています。
また、ミステリ史、女性の社会参加、都市論、消費者金融等、多岐にわたるテーマで講演会を開催し、大成功を収めました。
さらには朗読会の開催や、音楽学部の学生が、小説世界をイメージした曲を作曲演奏するコンサートなど、その活動は、読書の域にとどまらない広がりを見せています。
そのほか、初年度より、年に12〜15回程度発行している読書運動通信は、単なる活動報告、イベント告知のみならず、学生のおすすめの本や、教職員のエッセイ等、バラエティに富んだ内容を掲載しています。
現在では、学生への購入希望図書アンケート結果と、全学から寄贈された「友人知人に読ませたい本」を元に設置された「私たちの<今>を読むコーナー」も充実し、貸し出しランキング上位50位57冊のうちの22冊がこのコーナーの図書です。また、この22冊の中の13冊はテーマとして取り扱った宮部みゆき、村上春樹の著書であり、読書運動プロ
ジェクトの手ごたえが確かに感じられる結果となっています。
このように、年を追うごとに発展し、成果を上げて行く「読書運動プロジェクト」は、この読書の危機の時代に大学という場では何ができるかを最大限追求した試みです。 |