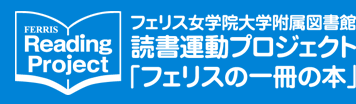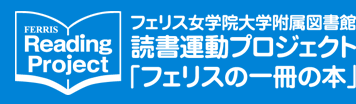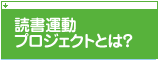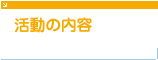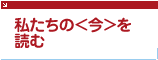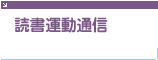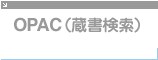|
 |
 |
 |
 |
● Q&A ●
|
 |
フェリスについて
1)フェリスは、全学何人?
3学部(文学部、国際交流学部、音楽学部)約2500人。
2)一科目は大体何人?
25人くらいのものが多い。最大でも80名程度。
3)HPを見るのにパスワード必要?
大学HPも、図書館HPも不要。
4)図書館の規模は?
緑園図書館は現在約27万冊所有。全面開架。閲覧席約530席。
|
 |
 |
 |
授業と読書運動の関係について
1)単位化しているか、必修か、何単位か?
2006年度から関連授業を開講する。
選択教養科目の1つで、各2単位。科目名は「今年の一冊(通年)」「読書からの発信(半期)」「読書とメディア(半期)」。
2)どこか1学部がメインか、音楽学部の教員、学生の関りは?
全学的な取り組みだが、テーマによっては文学部系になりがち。
が、テーマを社会的な切り口で取り扱ったり、音楽と関連付けたりして、常に全学的な関心をひきつけるよう努めている。
音楽学部の学生が主に活躍できるイベントとして、本を読んでイメージを作曲・演奏する「作曲・演奏コンサート」を開催している。また朗読会は声楽科の学生の参加率が高い。
音楽学部教員によるレクチャーコンサートも実施。
|
 |
 |
 |
活動について
1)一冊の本とは?
発足当初はテーマとして特定の図書を選び、文字通り「一冊の本」としたが、その「一冊」自体に関心が持てないと、そこから発展的な読書へ導くことが困難であることがわかった。そのため、中心となる図書は1冊選ぶが、それに限定せずにテーマに関する図書を幅広く扱うこととした。読書欲を刺激し、読書の習慣を育てる最初の一歩となる本というような意味で「一冊の本」をプロジェクトの名称としている。
2)何が目標か?
活字離れを解消し読書を習慣化させることにより、総合的読解力、文章力を向上させ、他者理解、複雑な思考力、多元的価値観を身に付け、さらには外に向かって発信できるようになること。
3)学生メンバーをどう集めるか、毎年何人くらい集まるか?
有志。大体10名前後。
4)テーマはどう決めるか?
プロジェクト内で何点か候補を出しておき、それを全学アンケートで決める。
5)教職員はどうかかわるか?
学生が企画立案し、教員が内容的アドバイス、図書館職員が実務的フォロー。
6)各イベントに対する学生の反応は?
概ね良い。学生メンバー企画立案なので、一般学生との温度差があまりないようだ。
|
 |
 |
 |
効果について
1)よく本が読まれるようになったか?
プロジェクト開始の2002年以降、学生一人あたりの貸出し冊数が約3.5冊も増えた。
また、テーマとして取り上げた著者の本が貸し出しランキング上位を占めている。
2)学生に文章力、読解力、思考力がついたか?
数量では図りがたいが、文章力、読解力、思考力が伸びていれば創作コンクールや感想文コンクールの応募点数、出来栄えともに向上するであろうし、授業レポートにも反映するのではないか。
3)就職に何か良い影響があったか?
まだ4年目なので見えてこない。が、思考力、文章力をつけることは就職のみならず、その後の人生にも良い影響があると思われる。また、読書運動を通じて朗読や開き読み(読み聞かせ)といった新たな境地を開いた学生もおり、将来への選択肢を広げたとも言える。
|